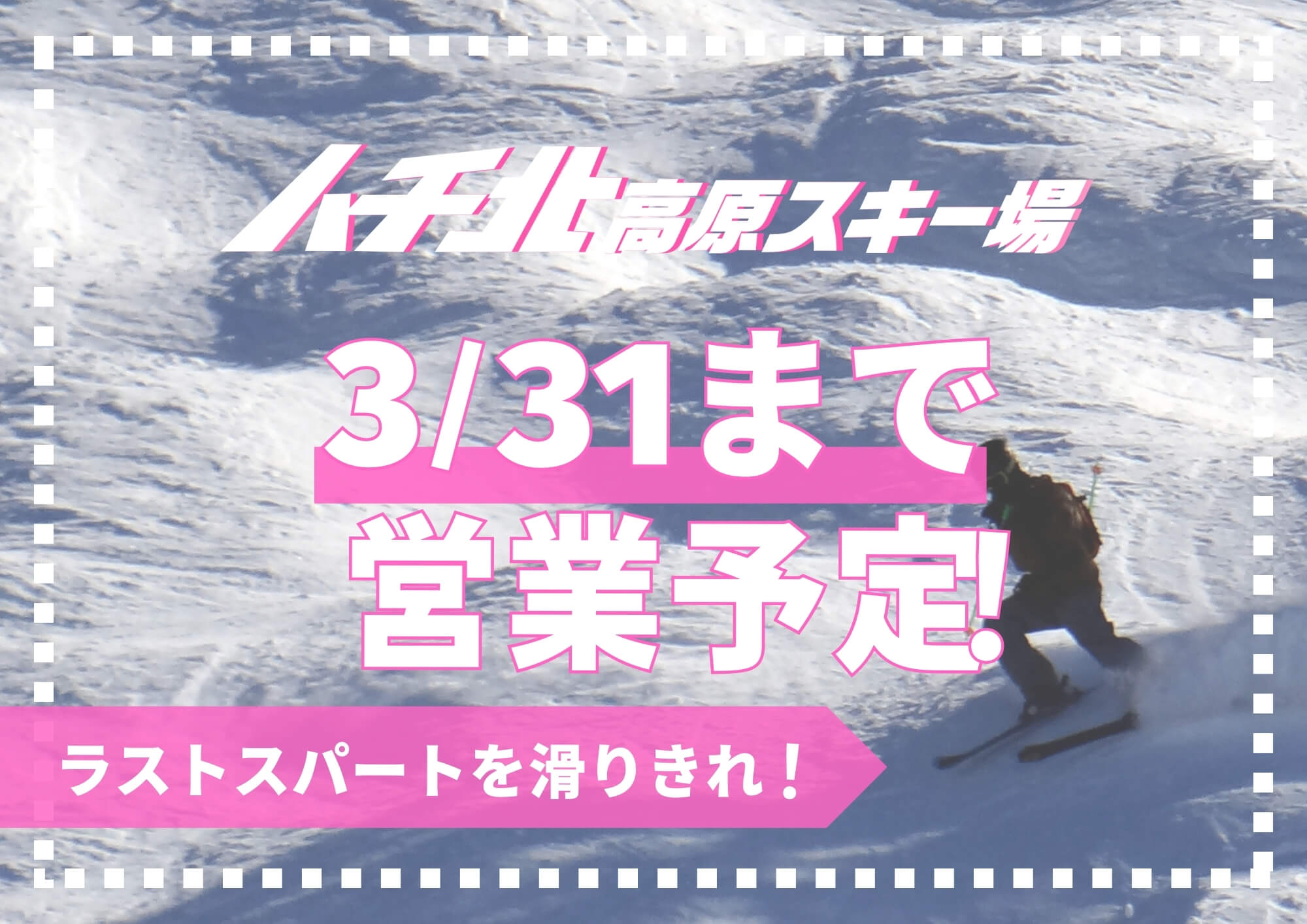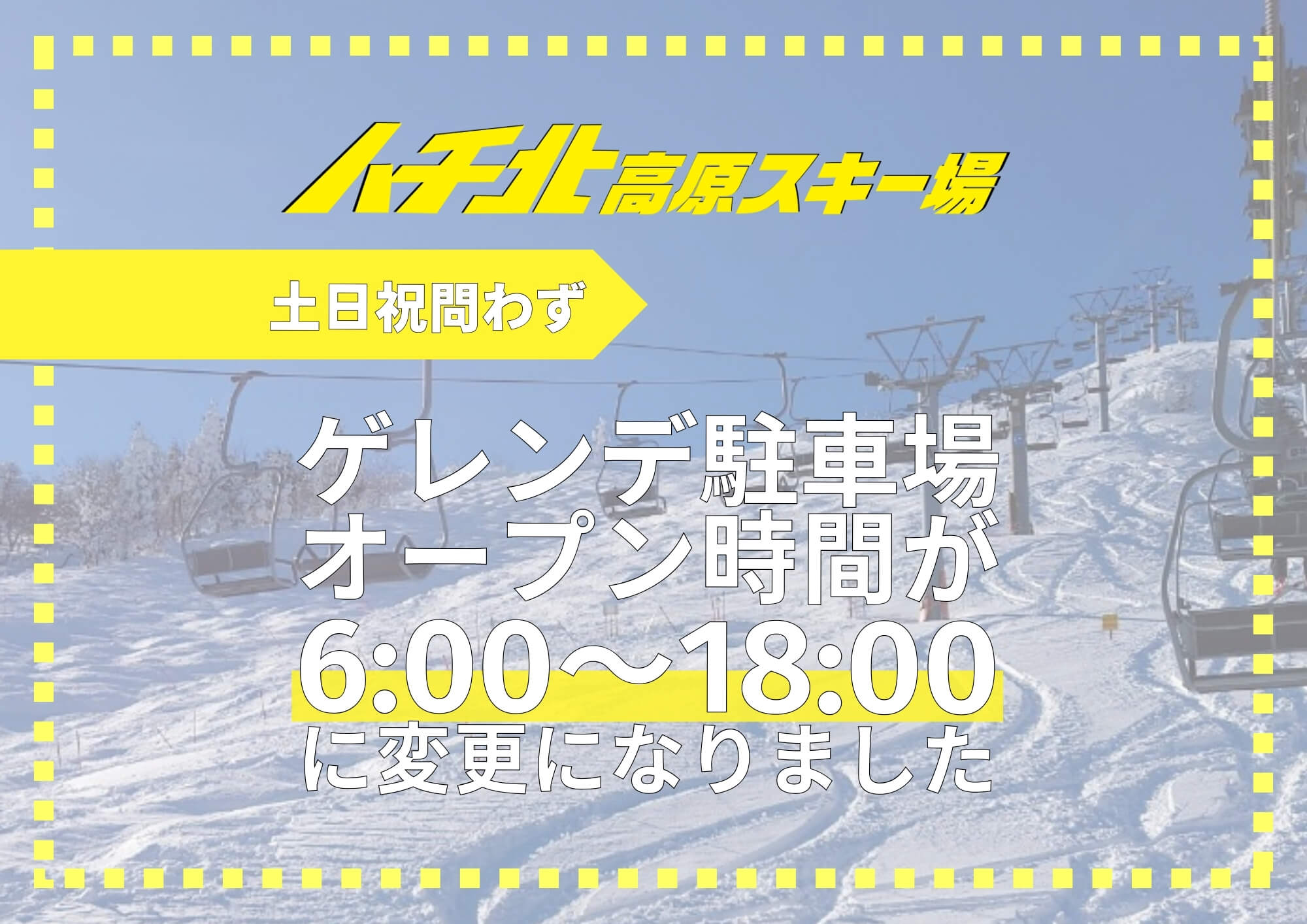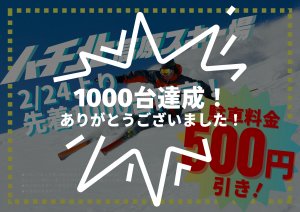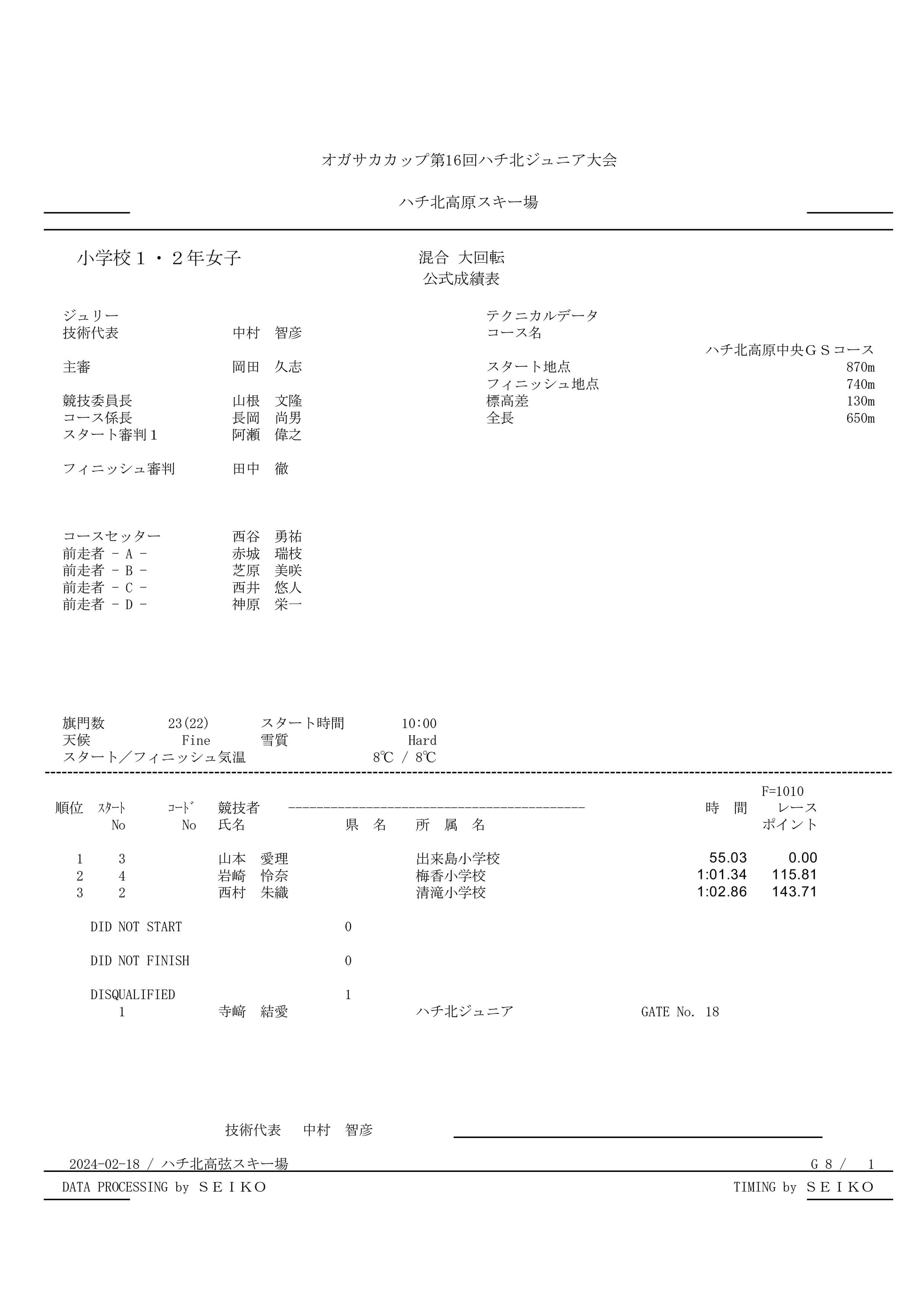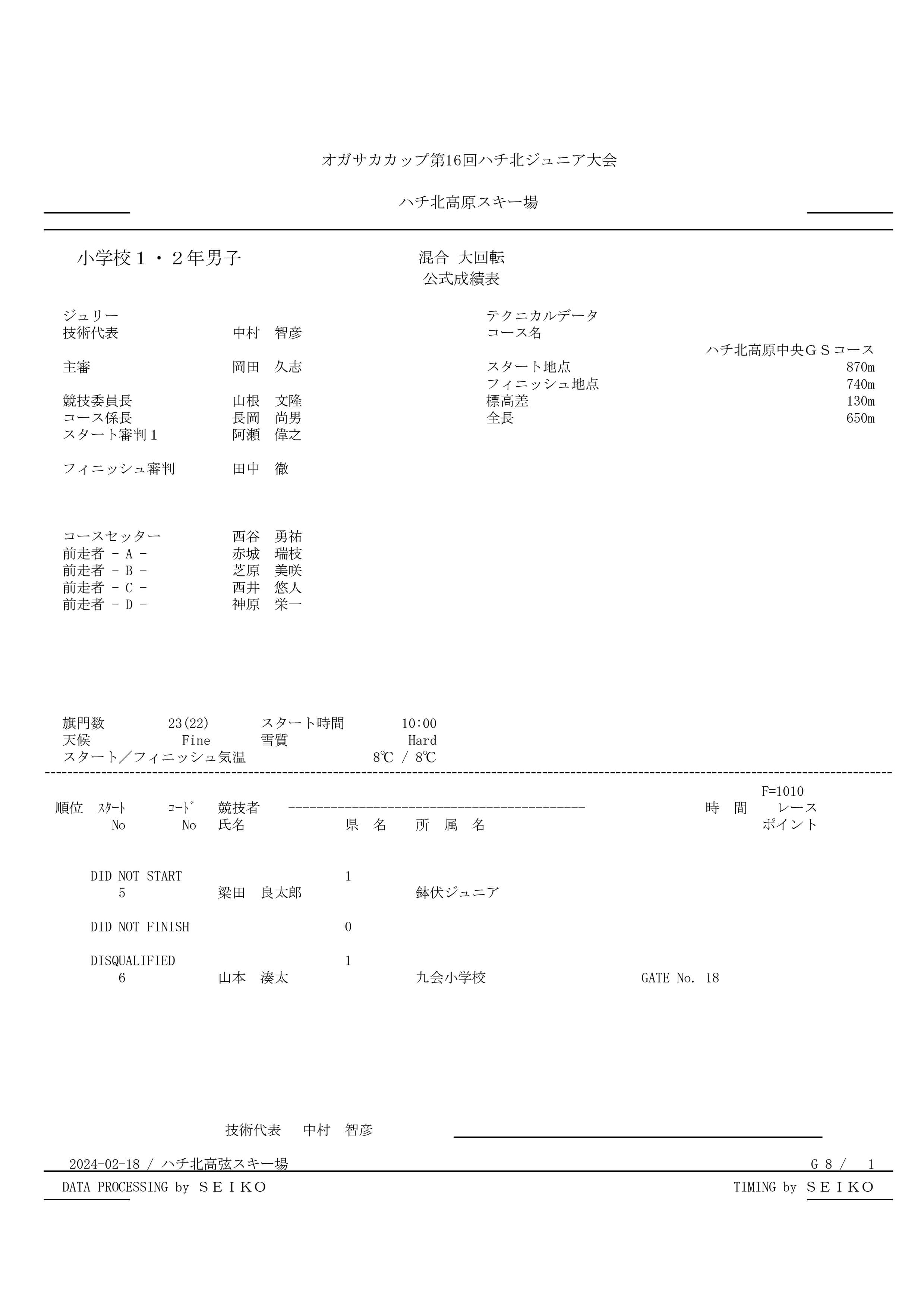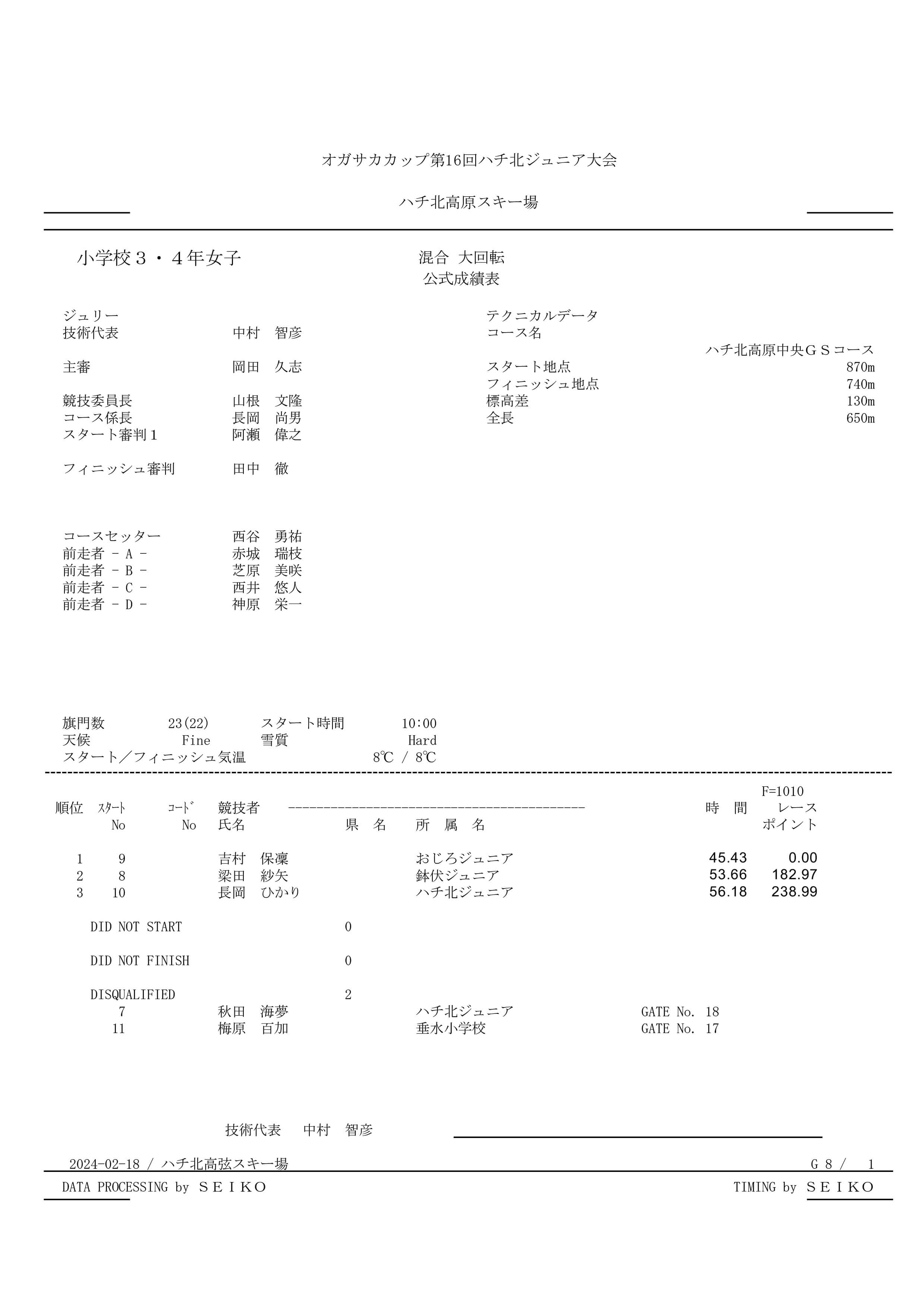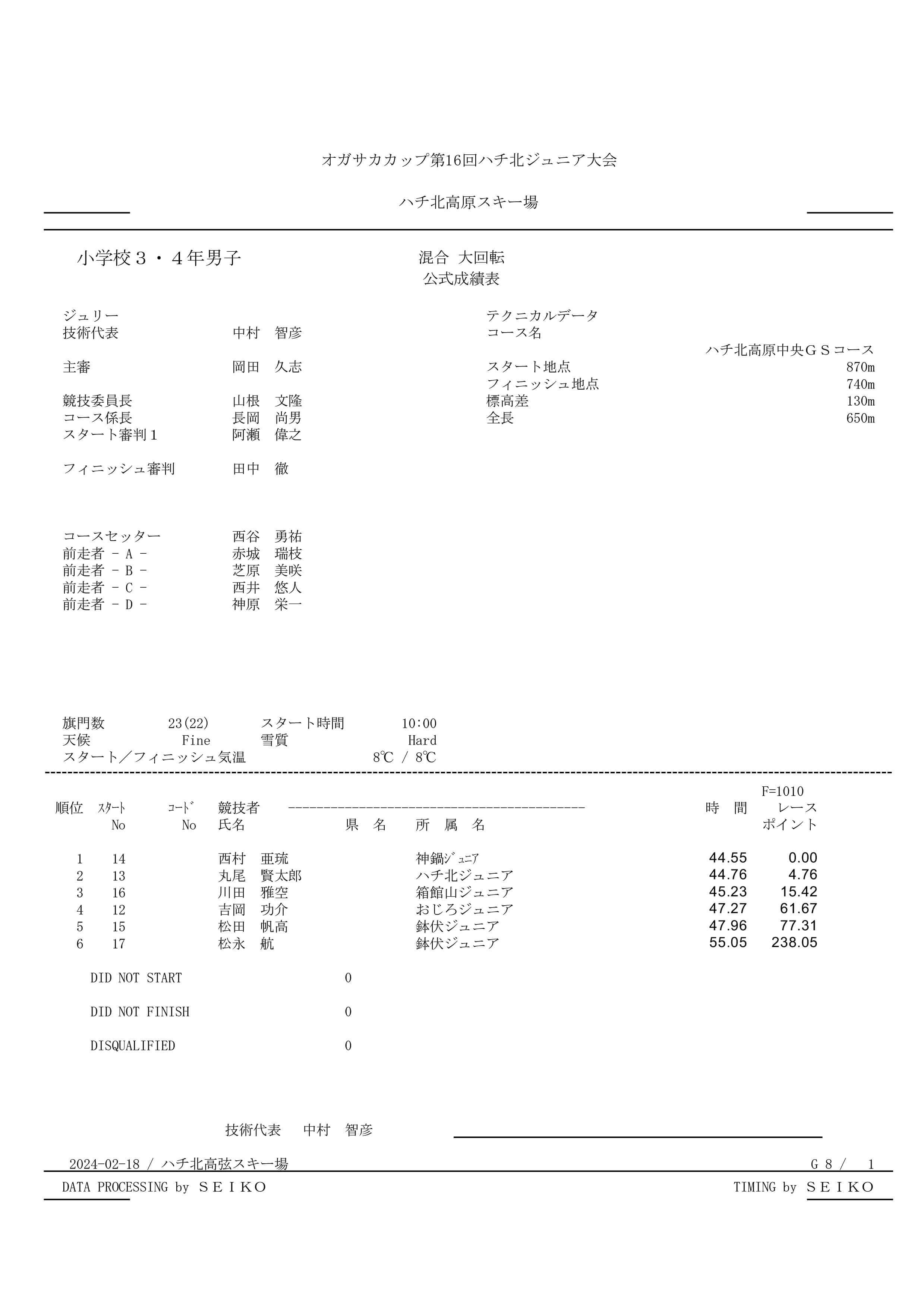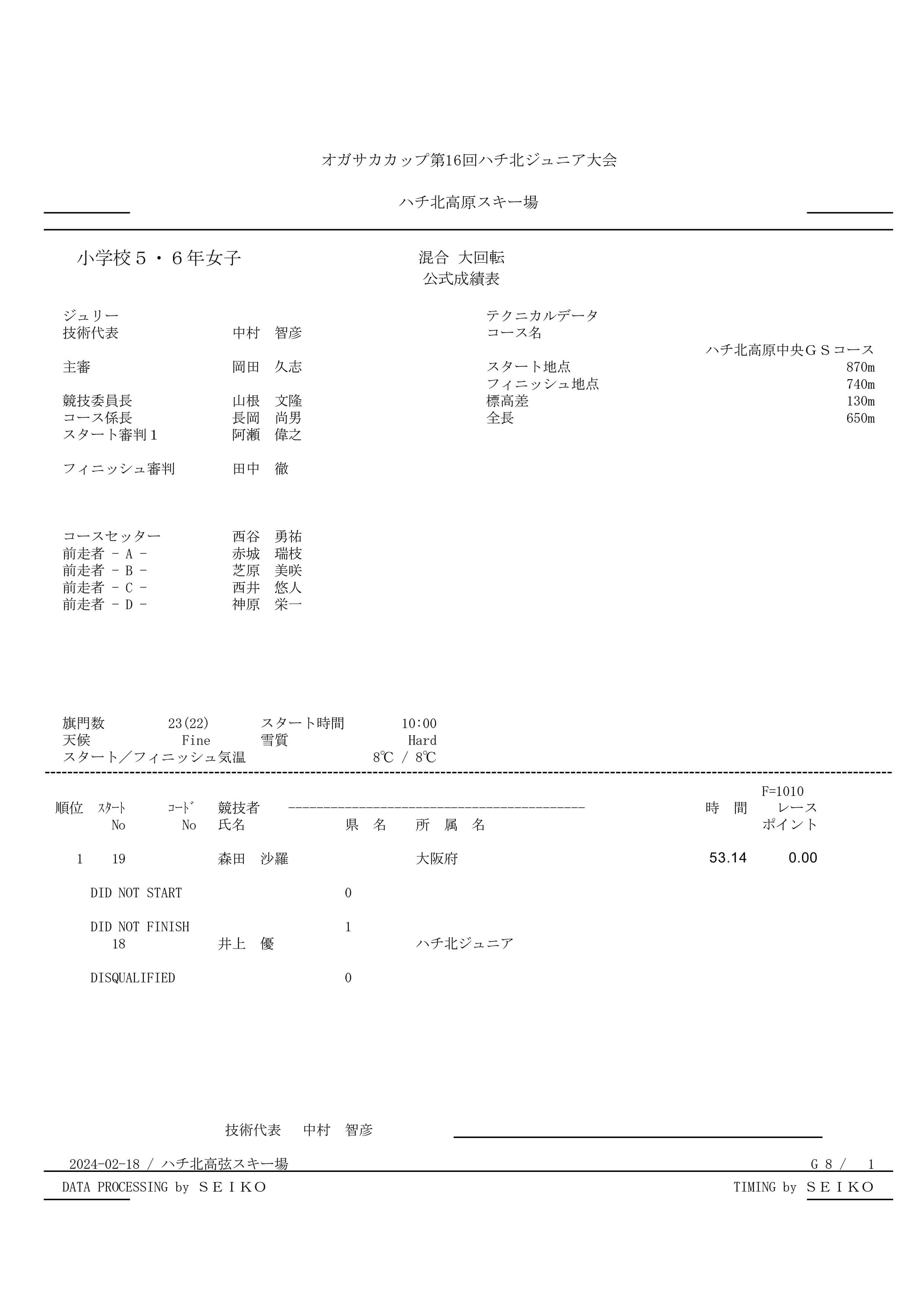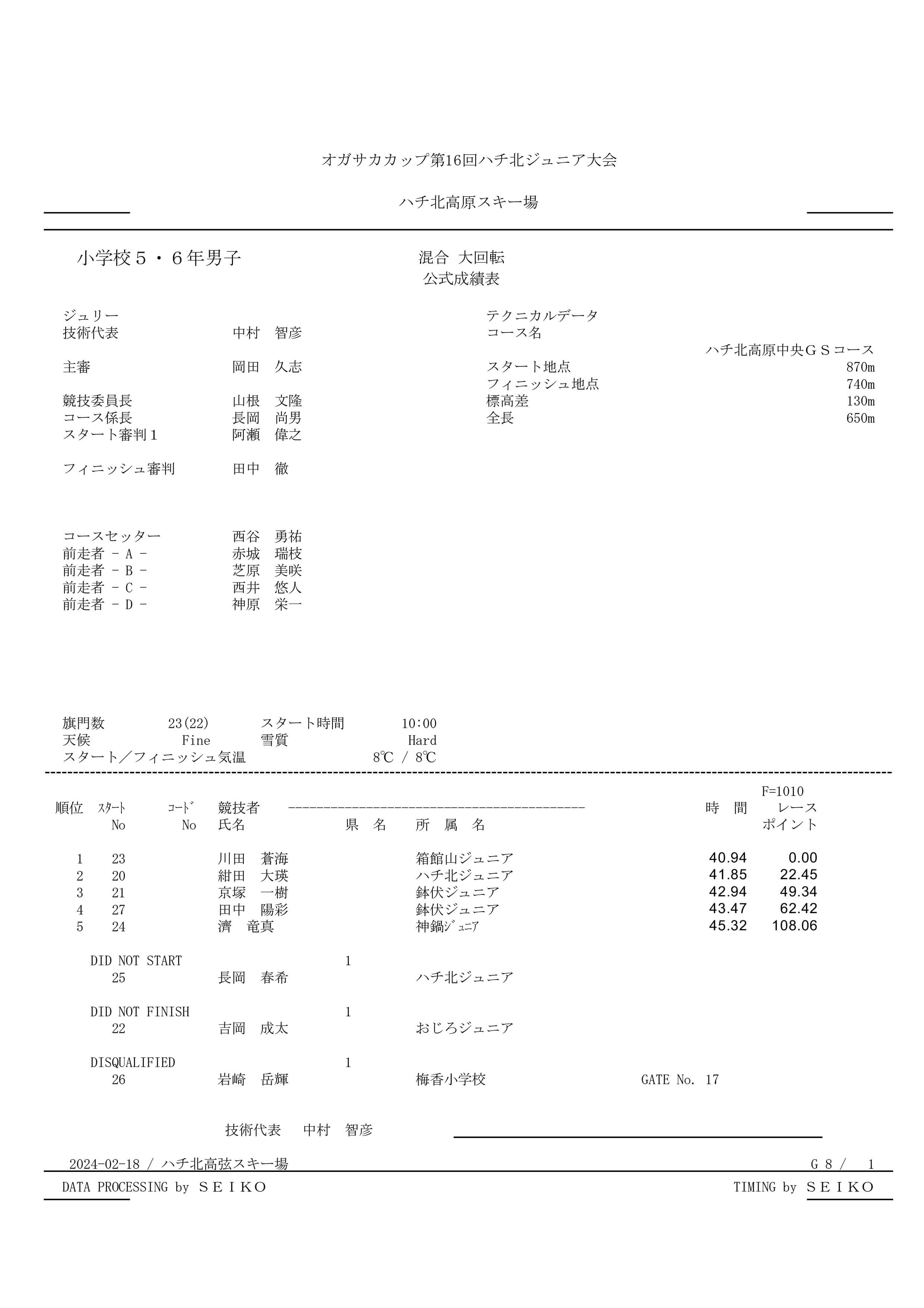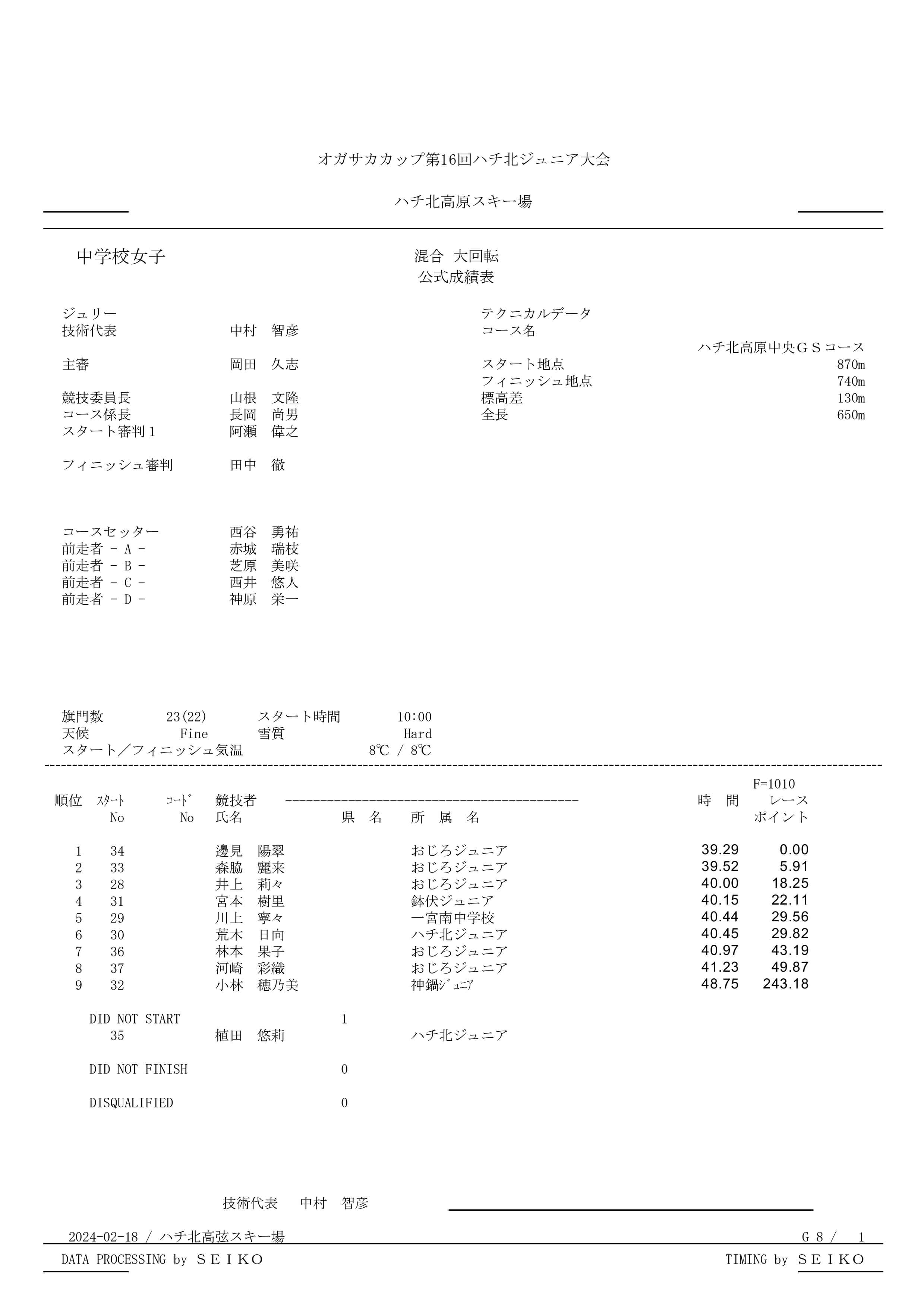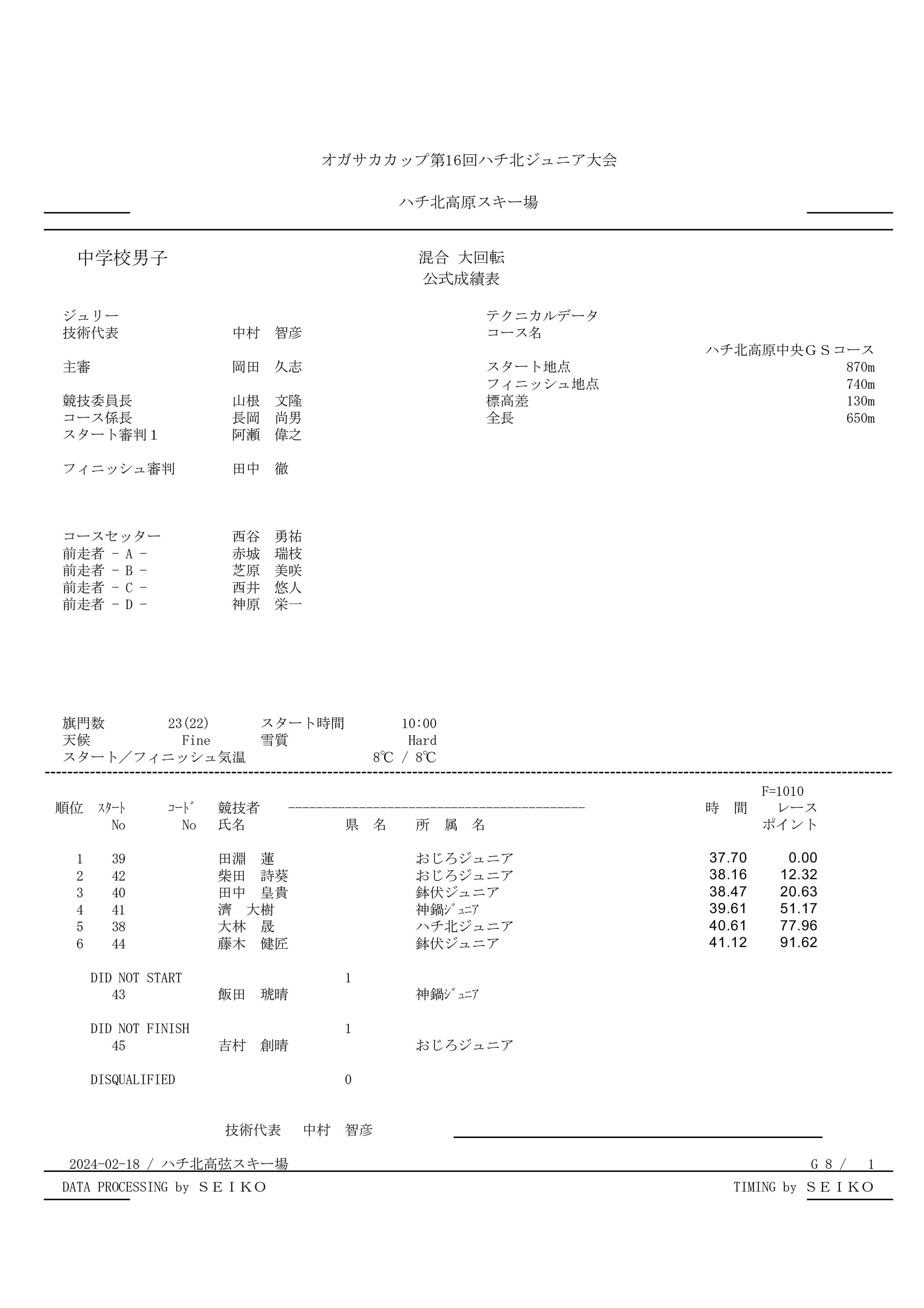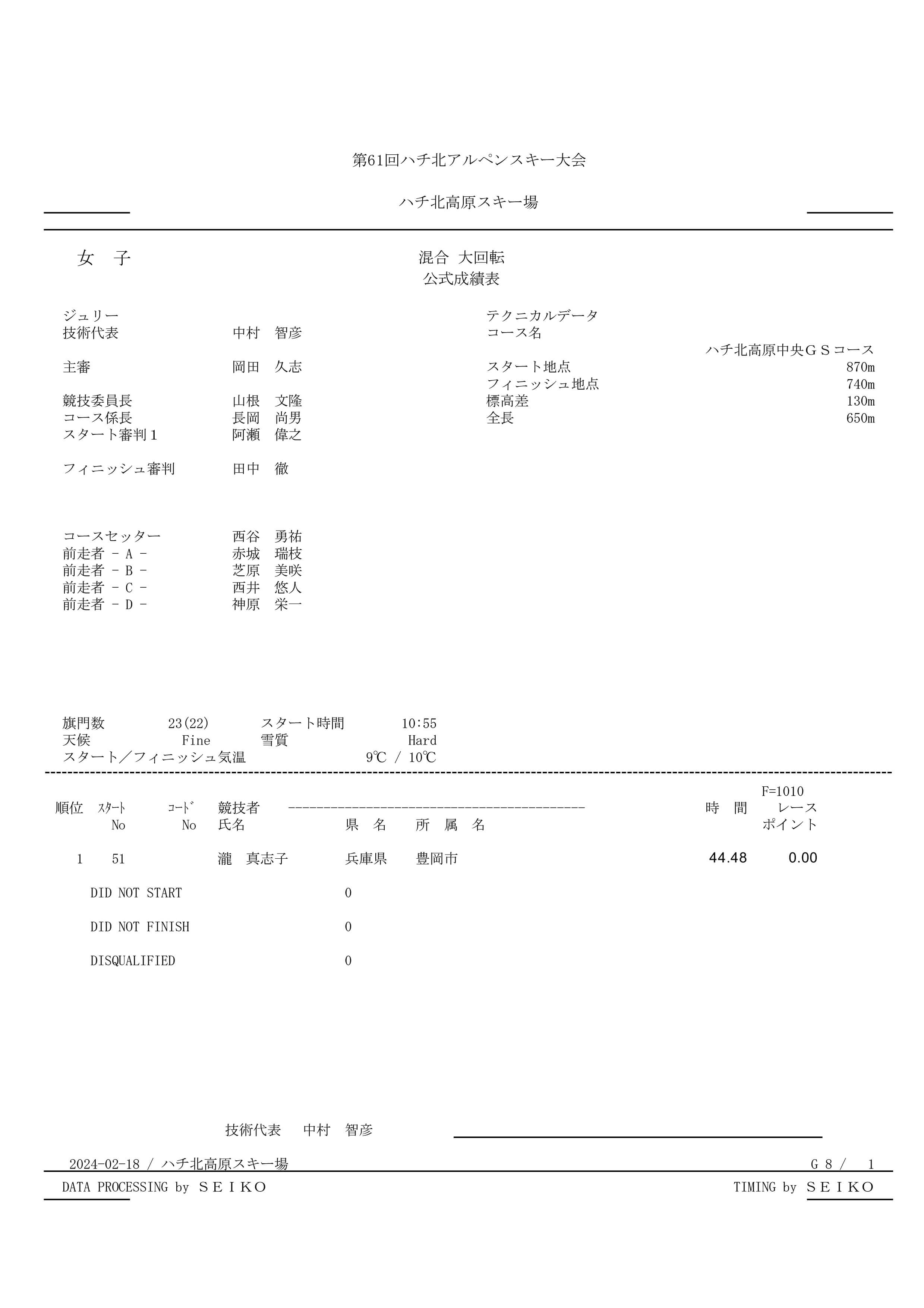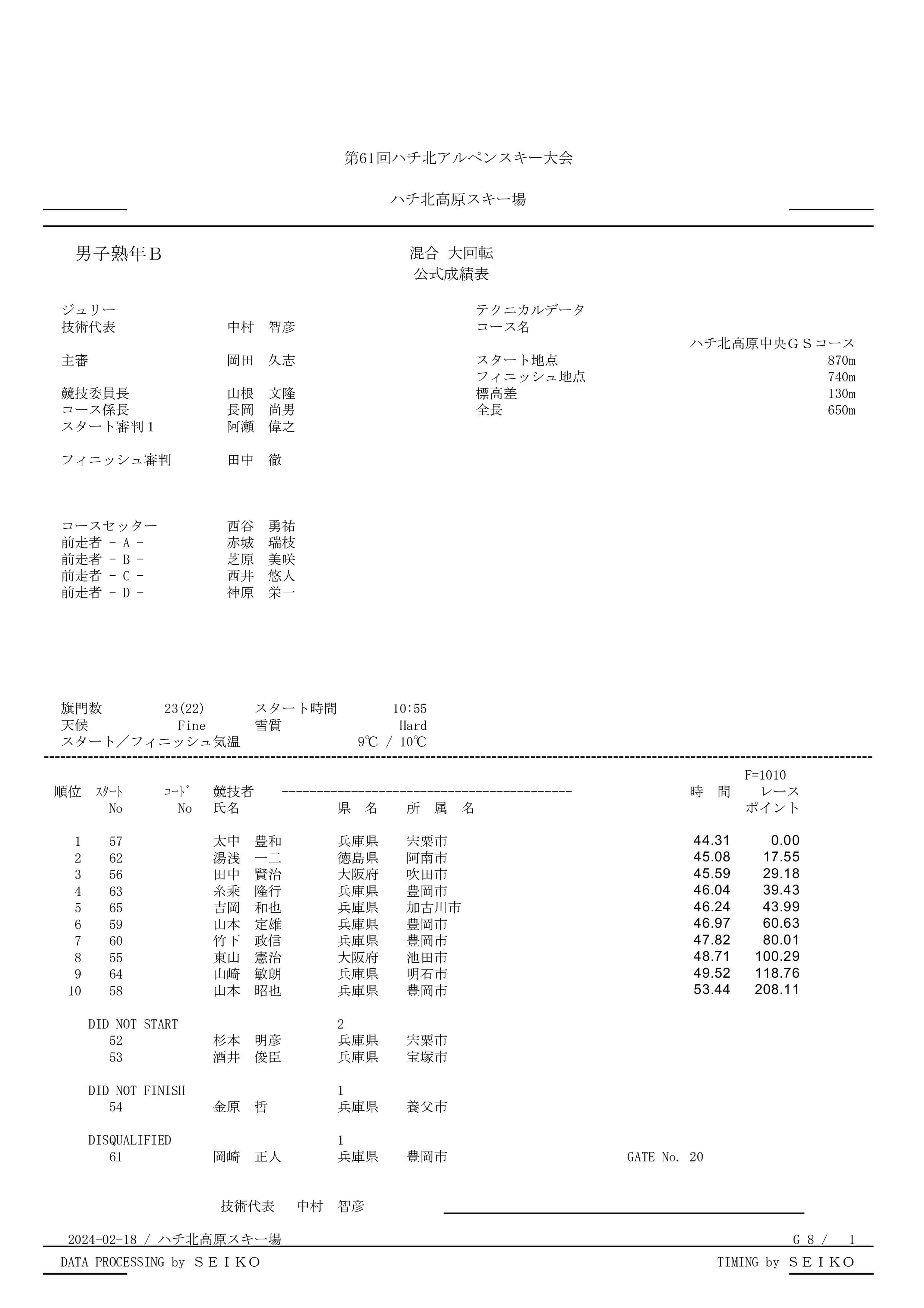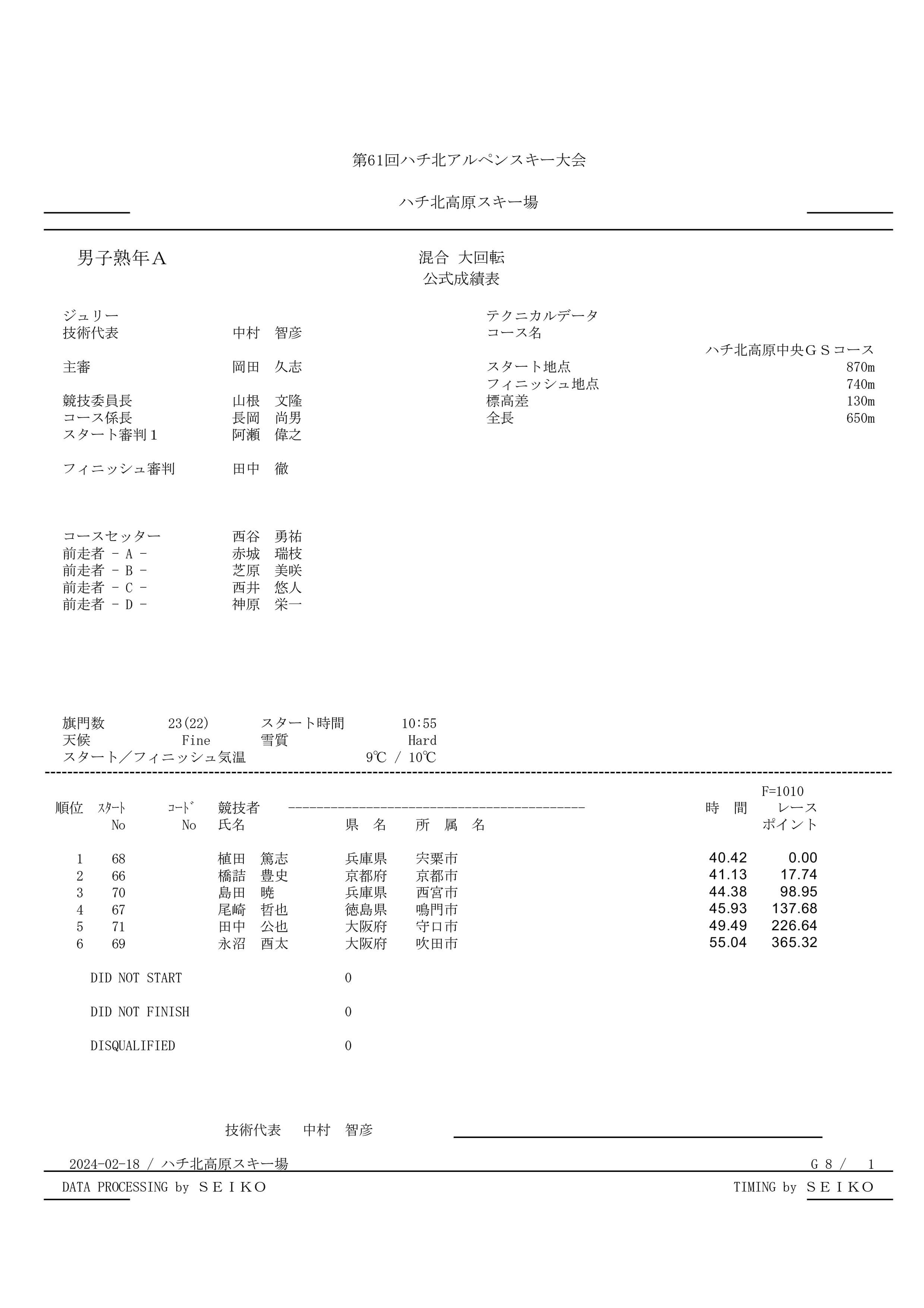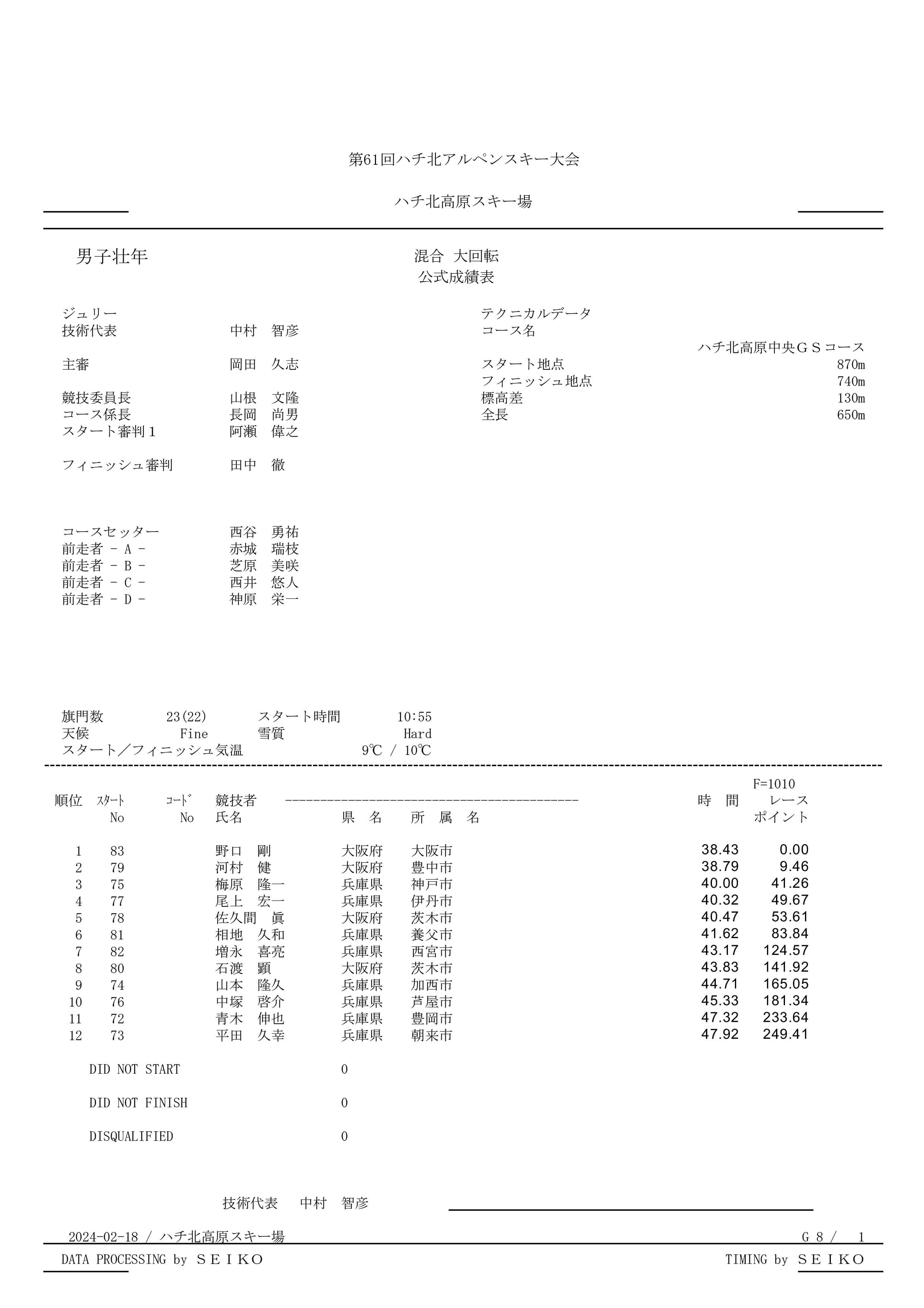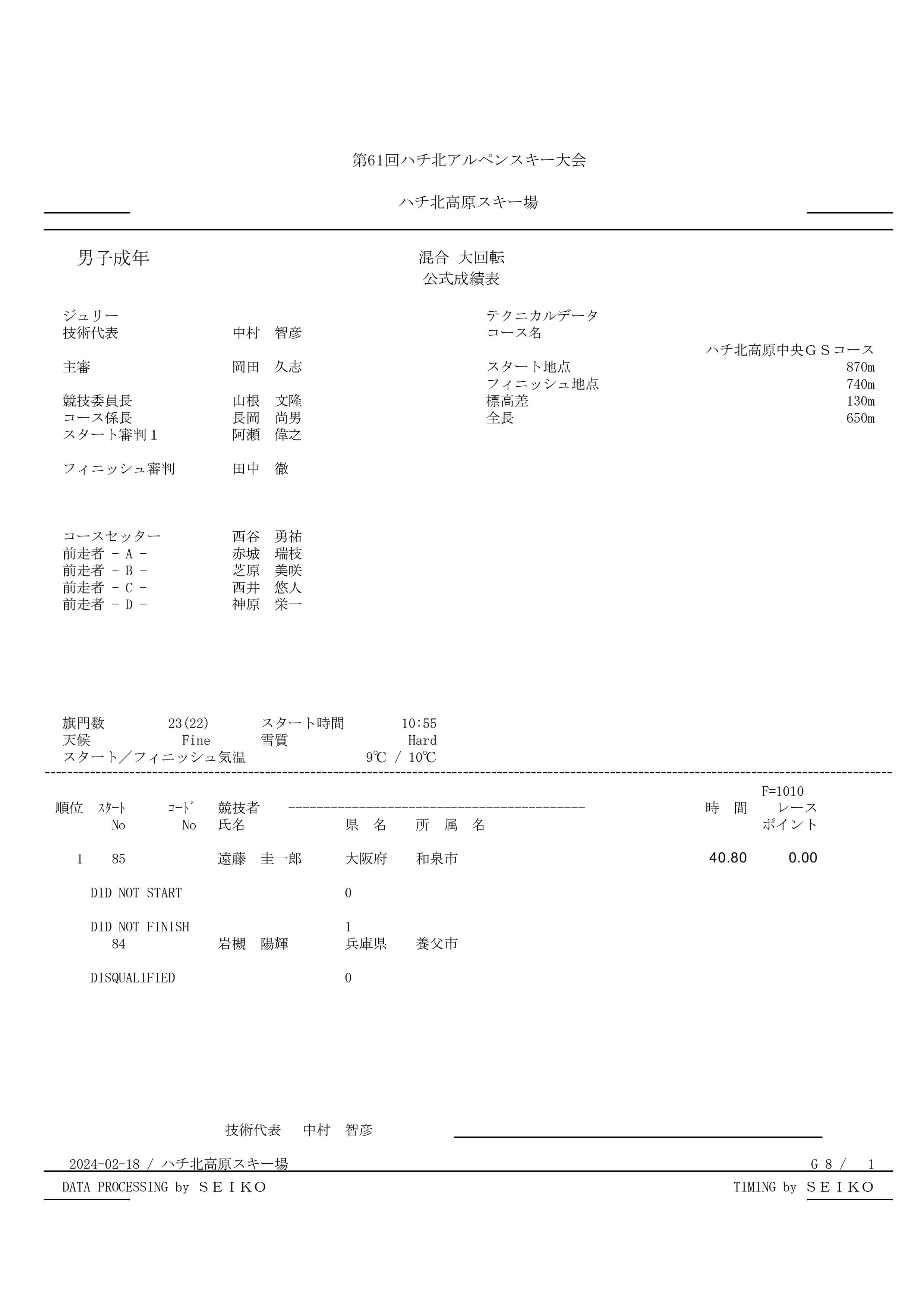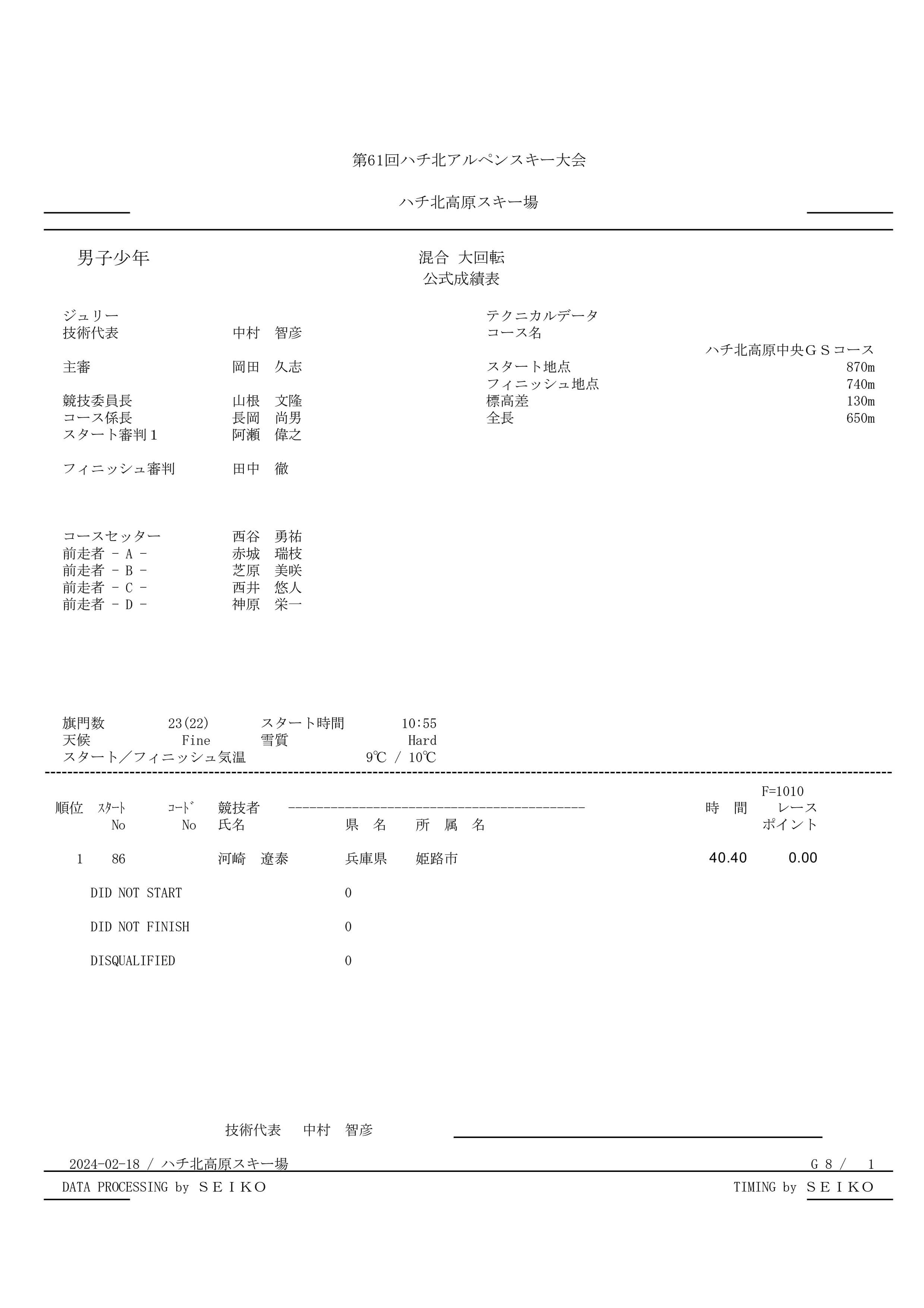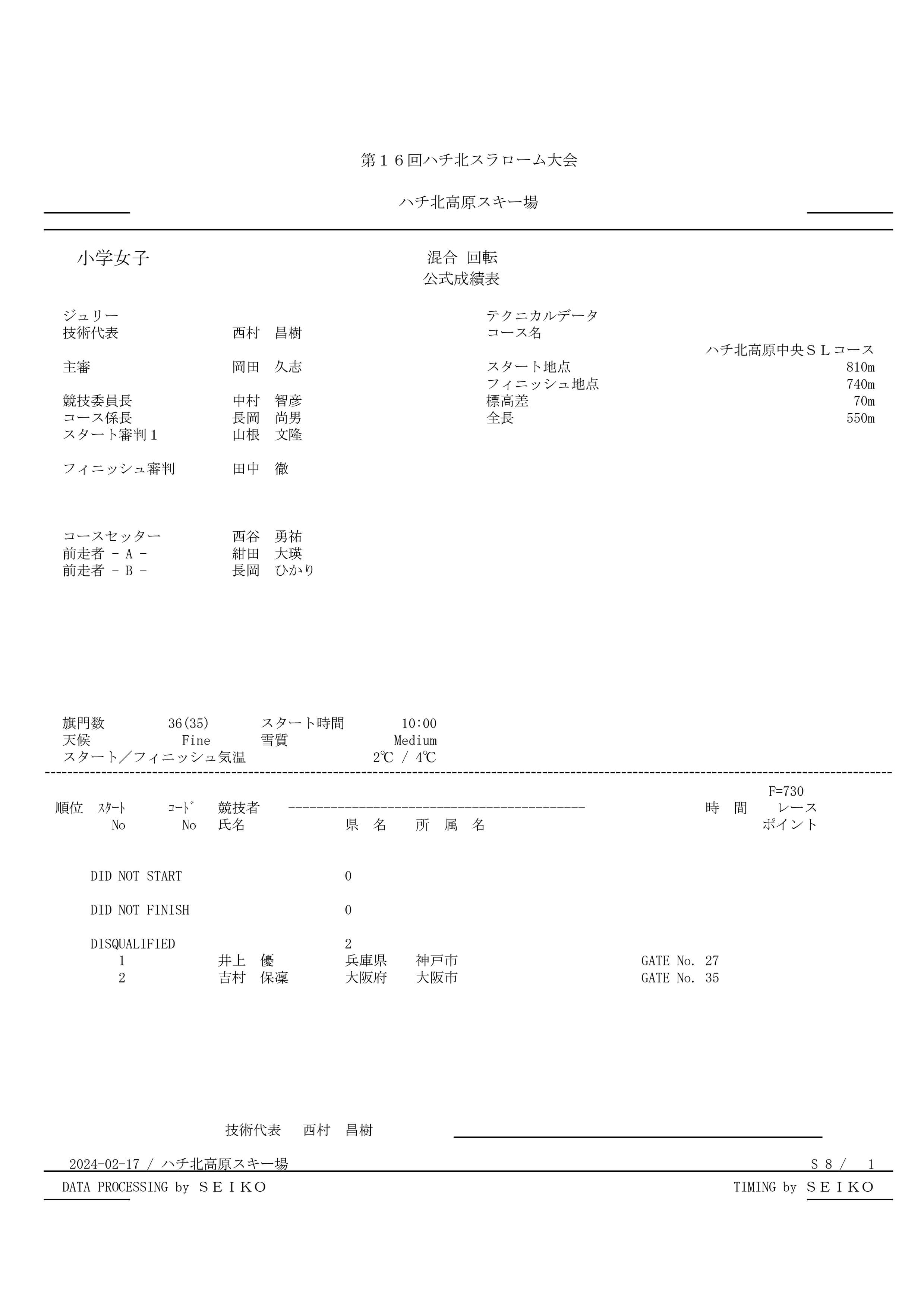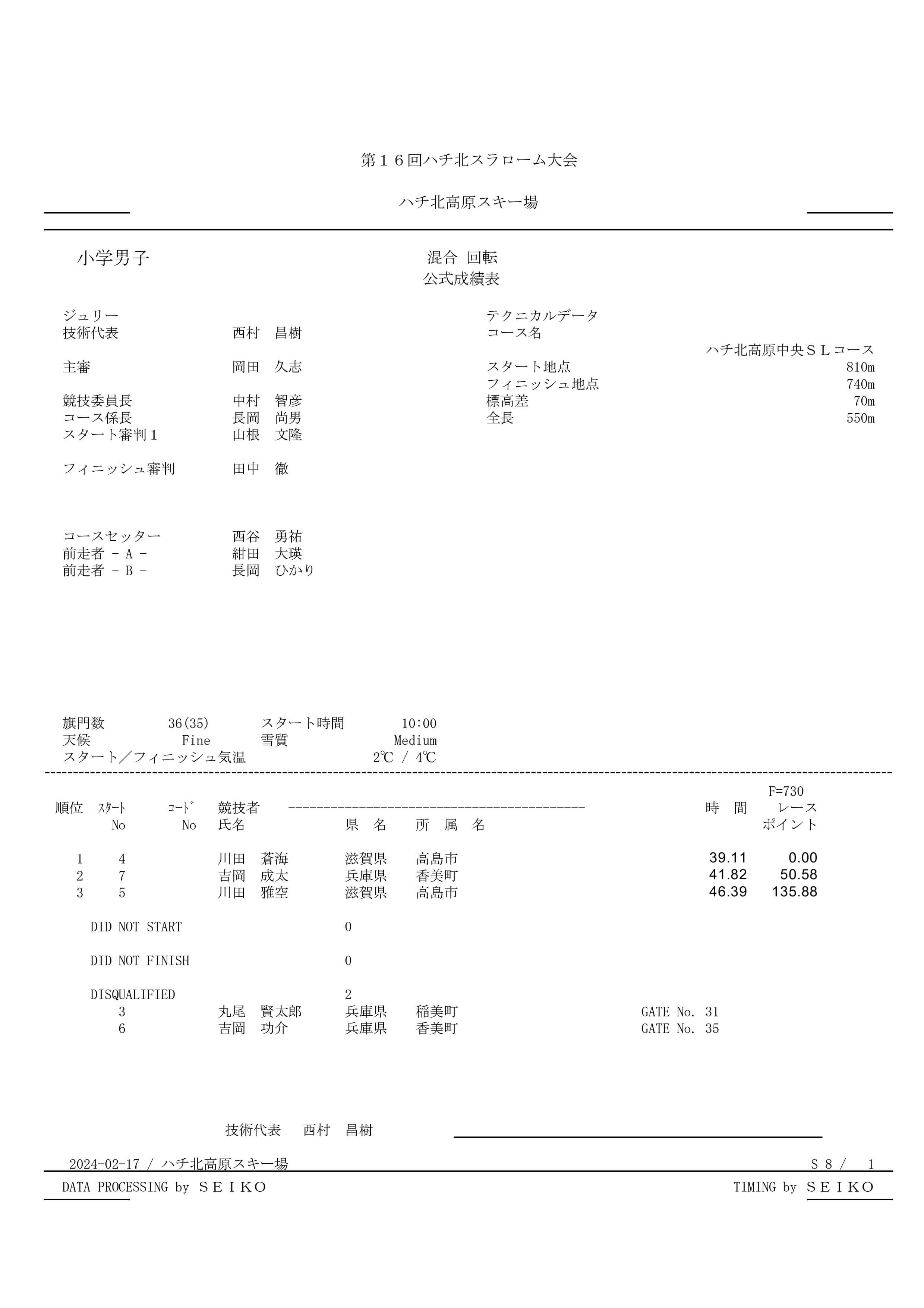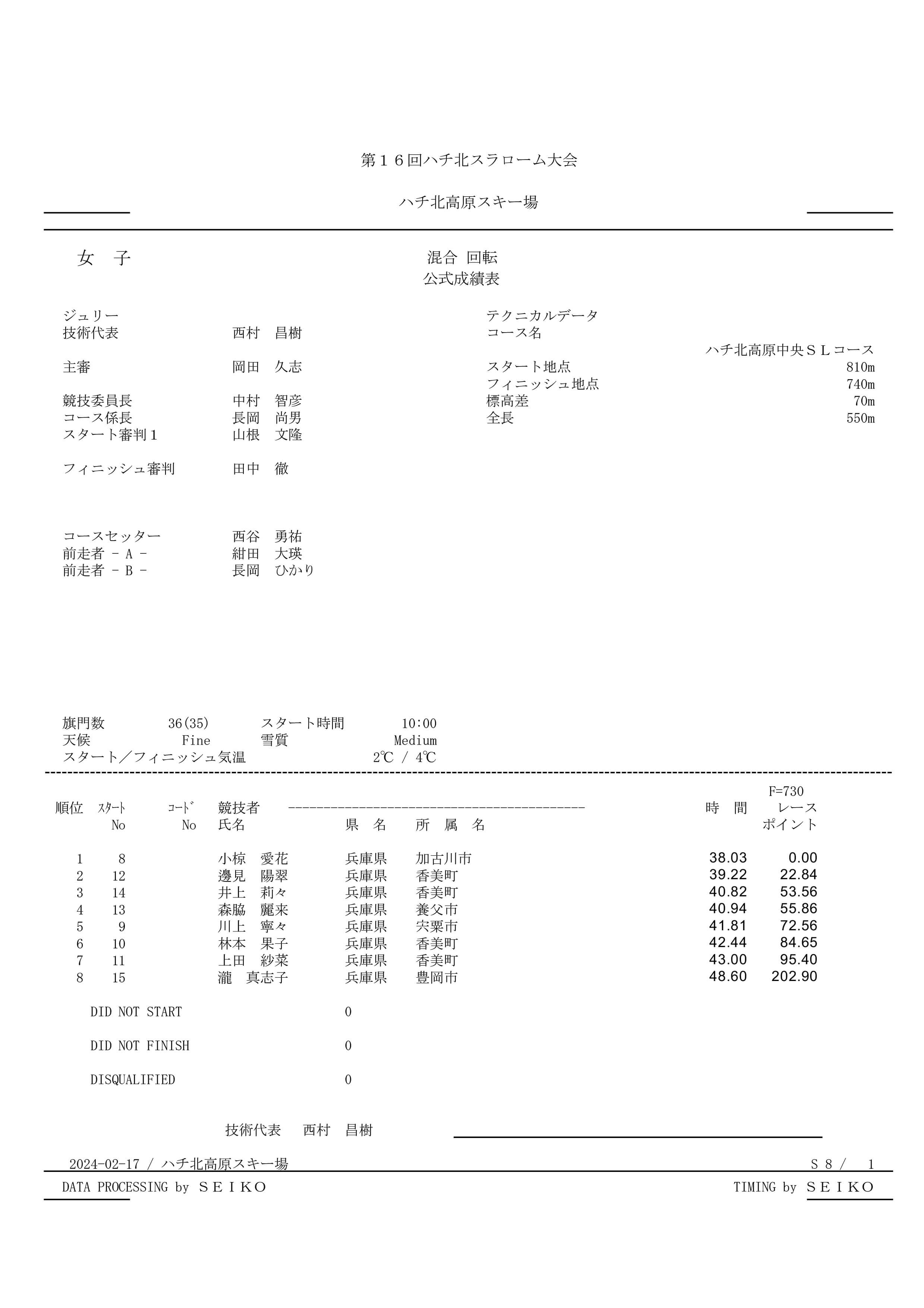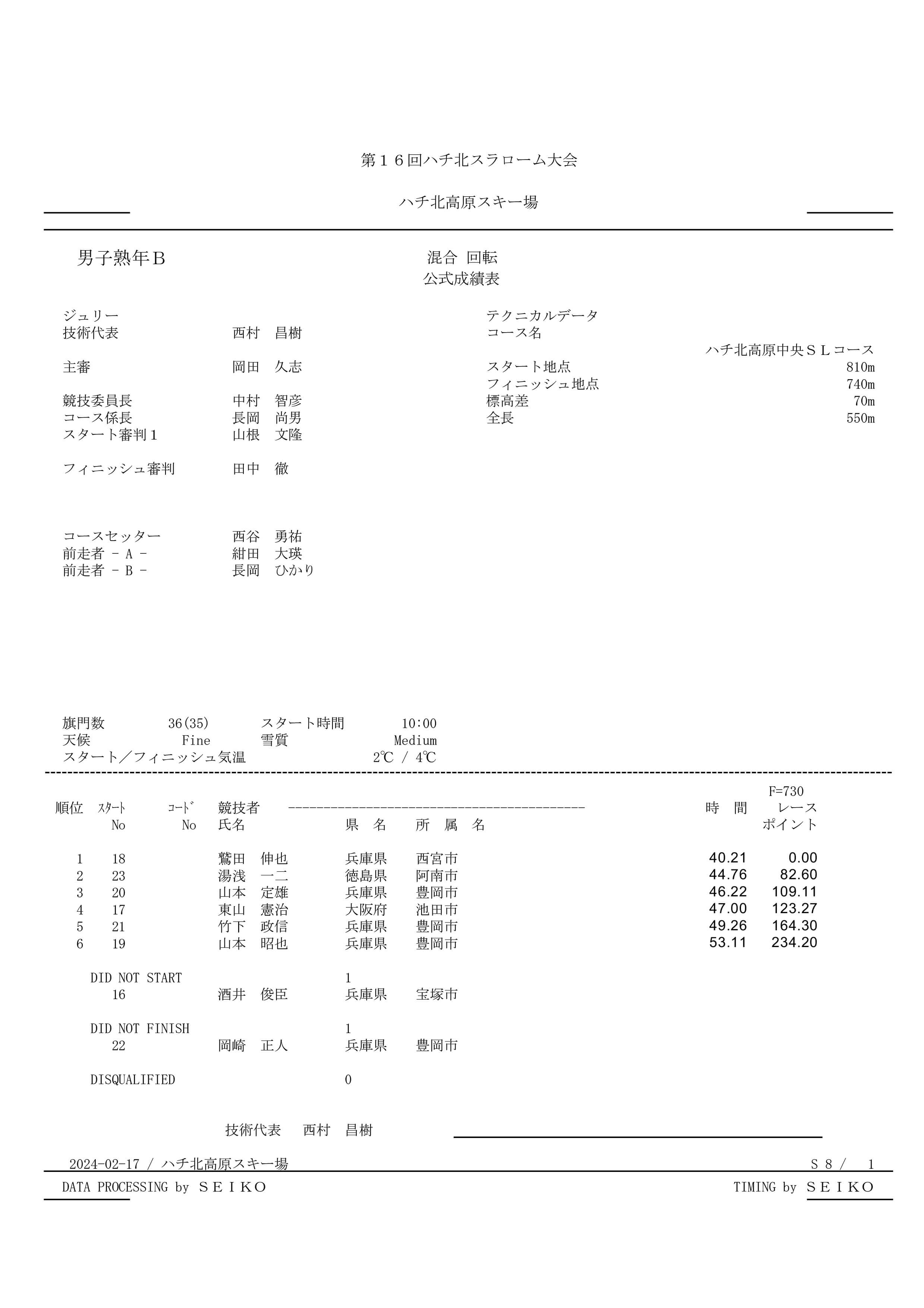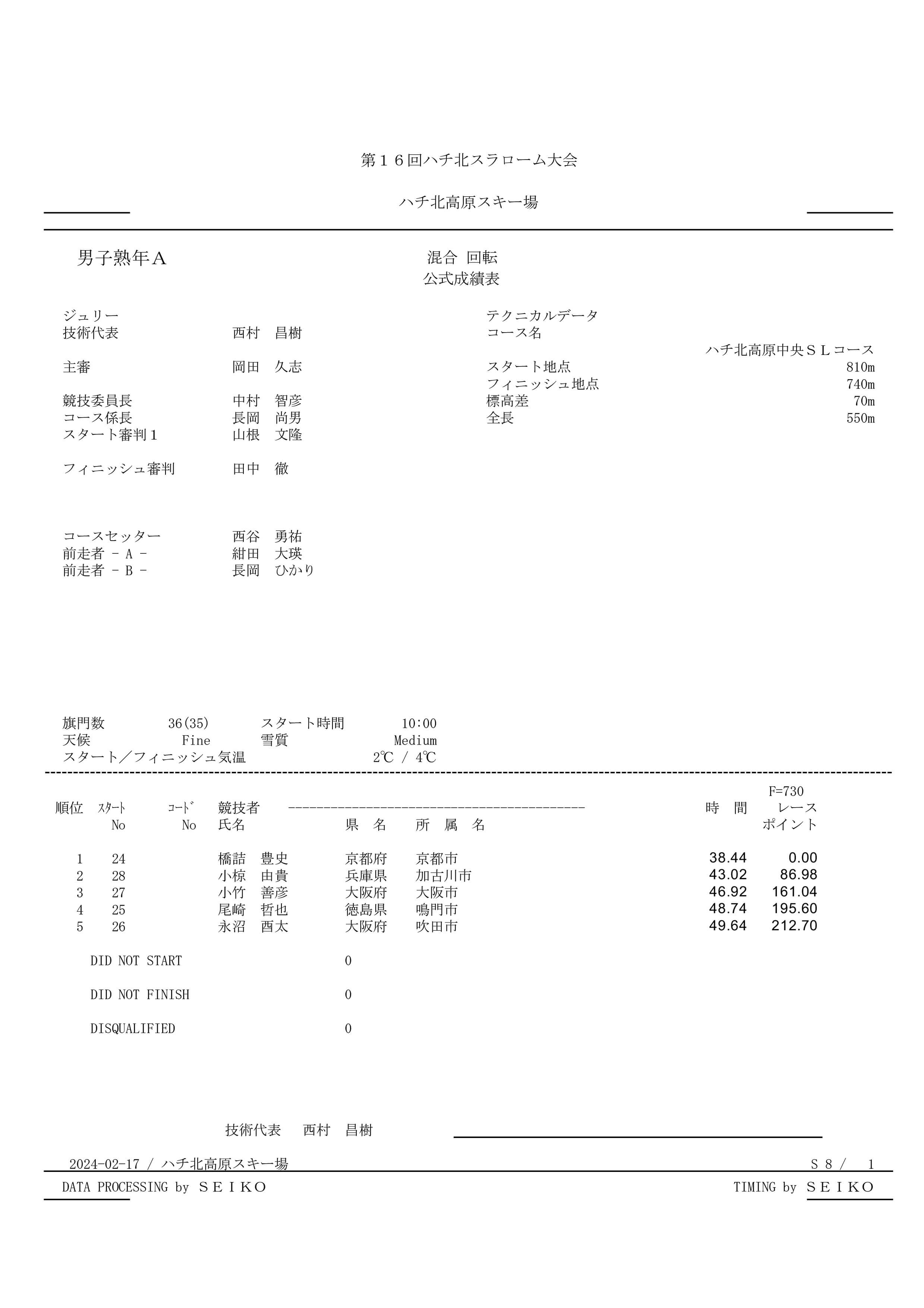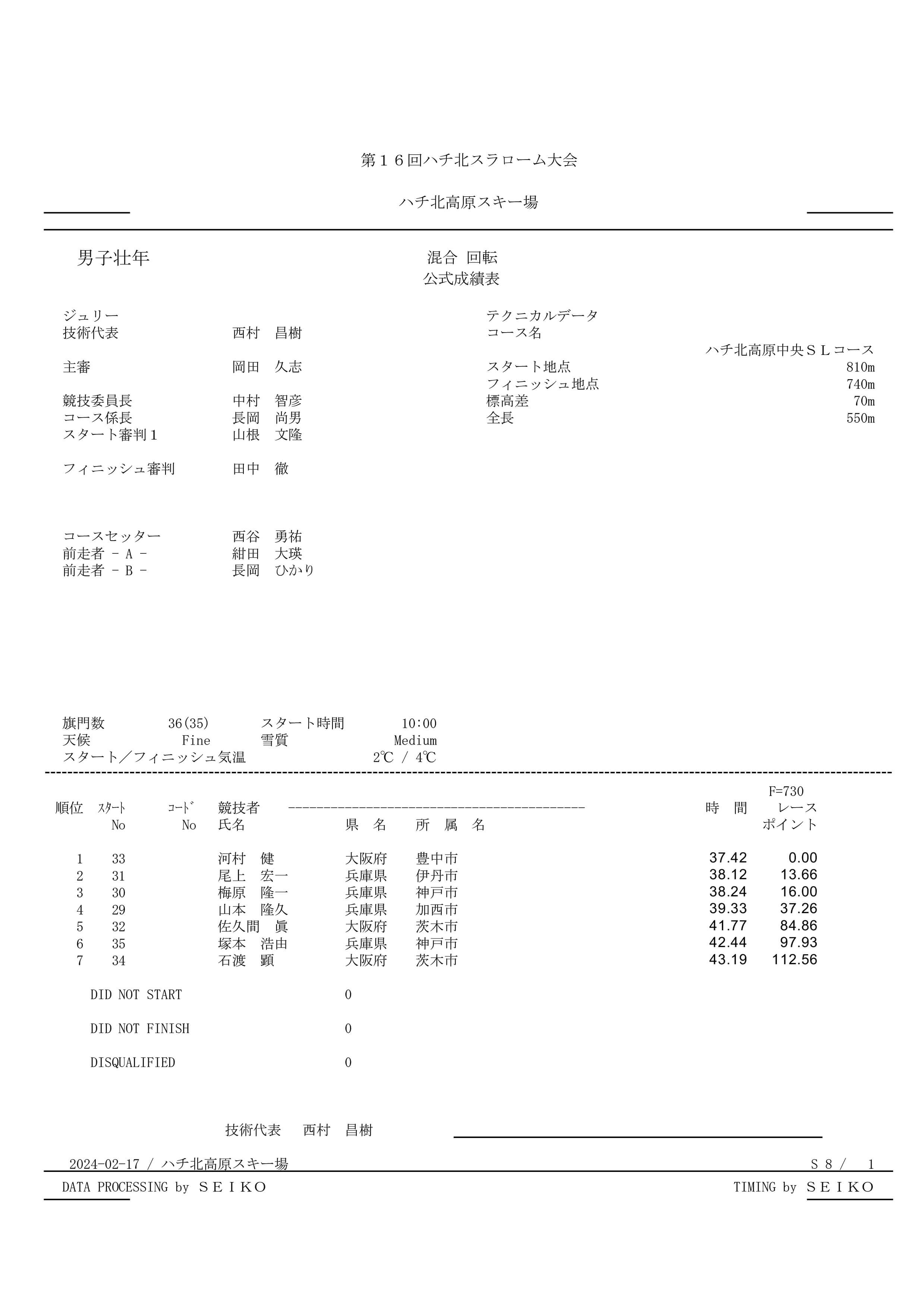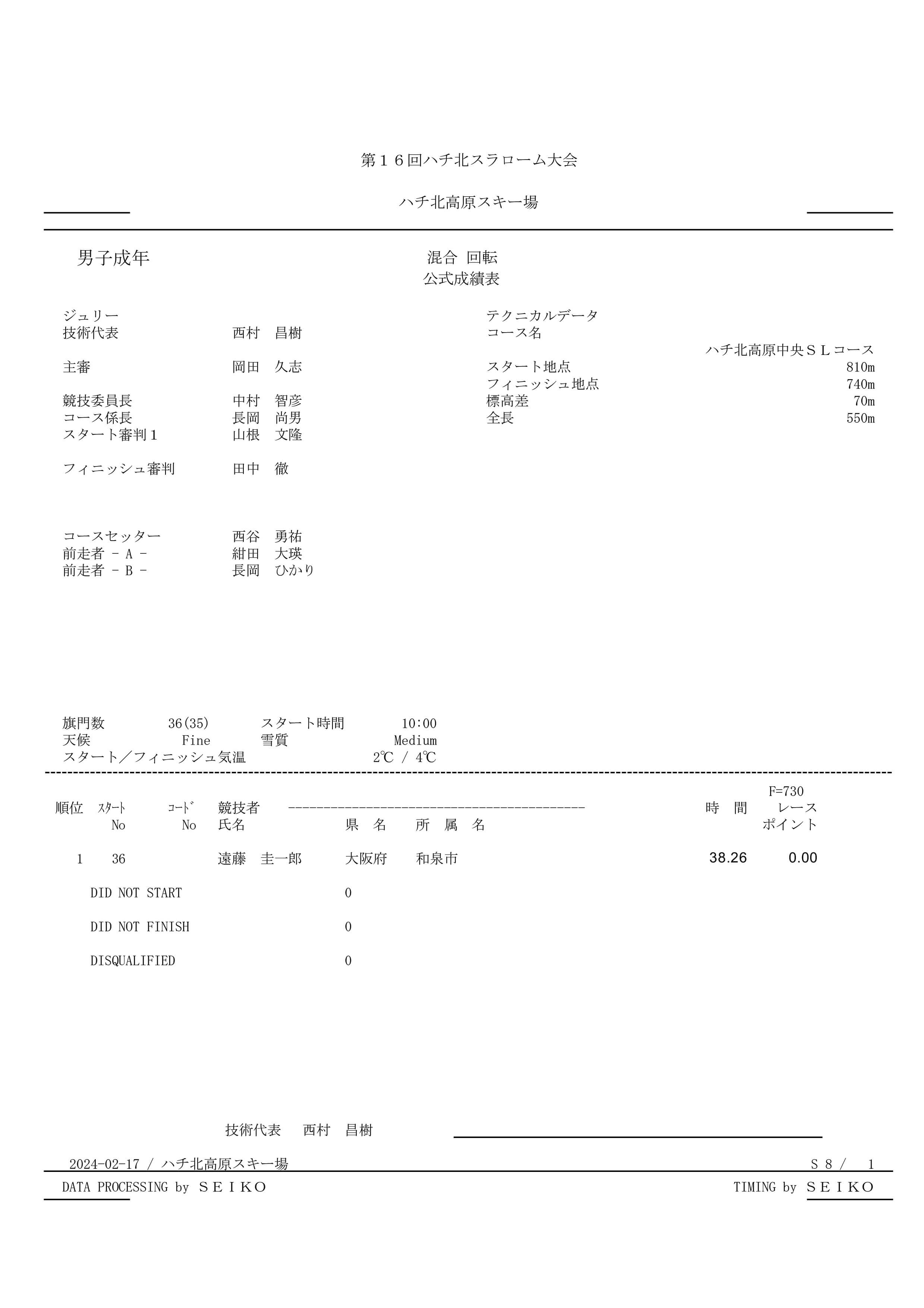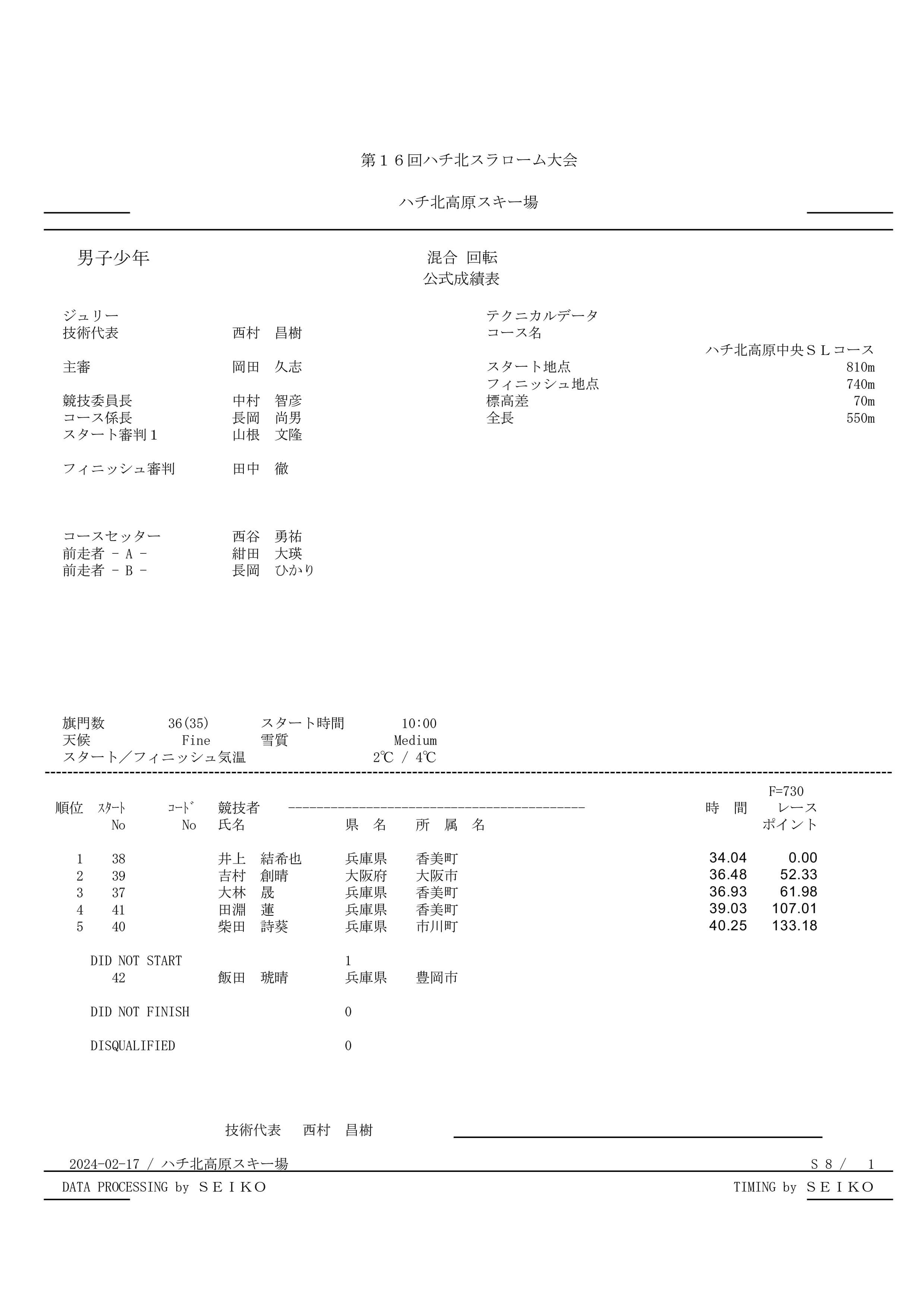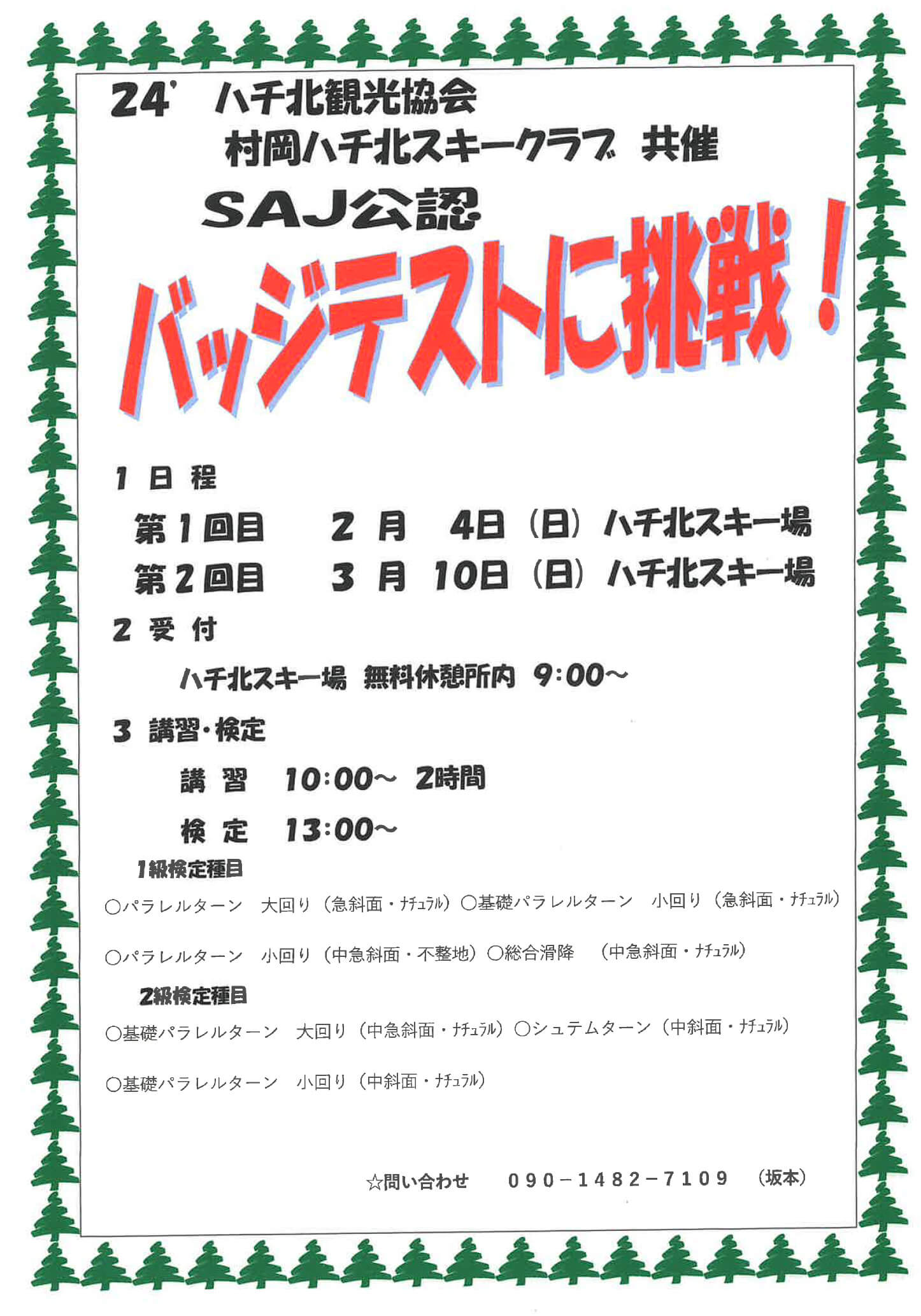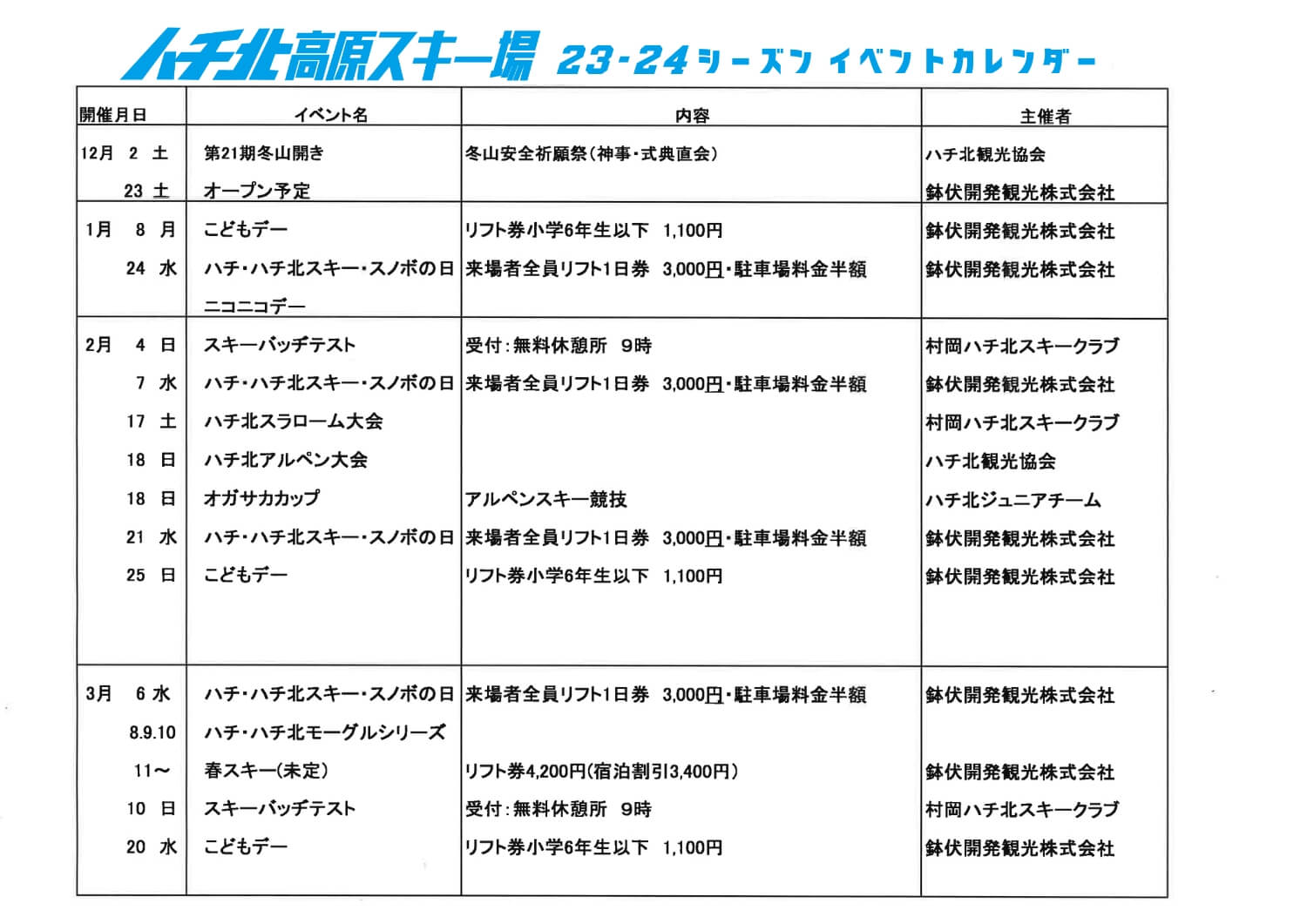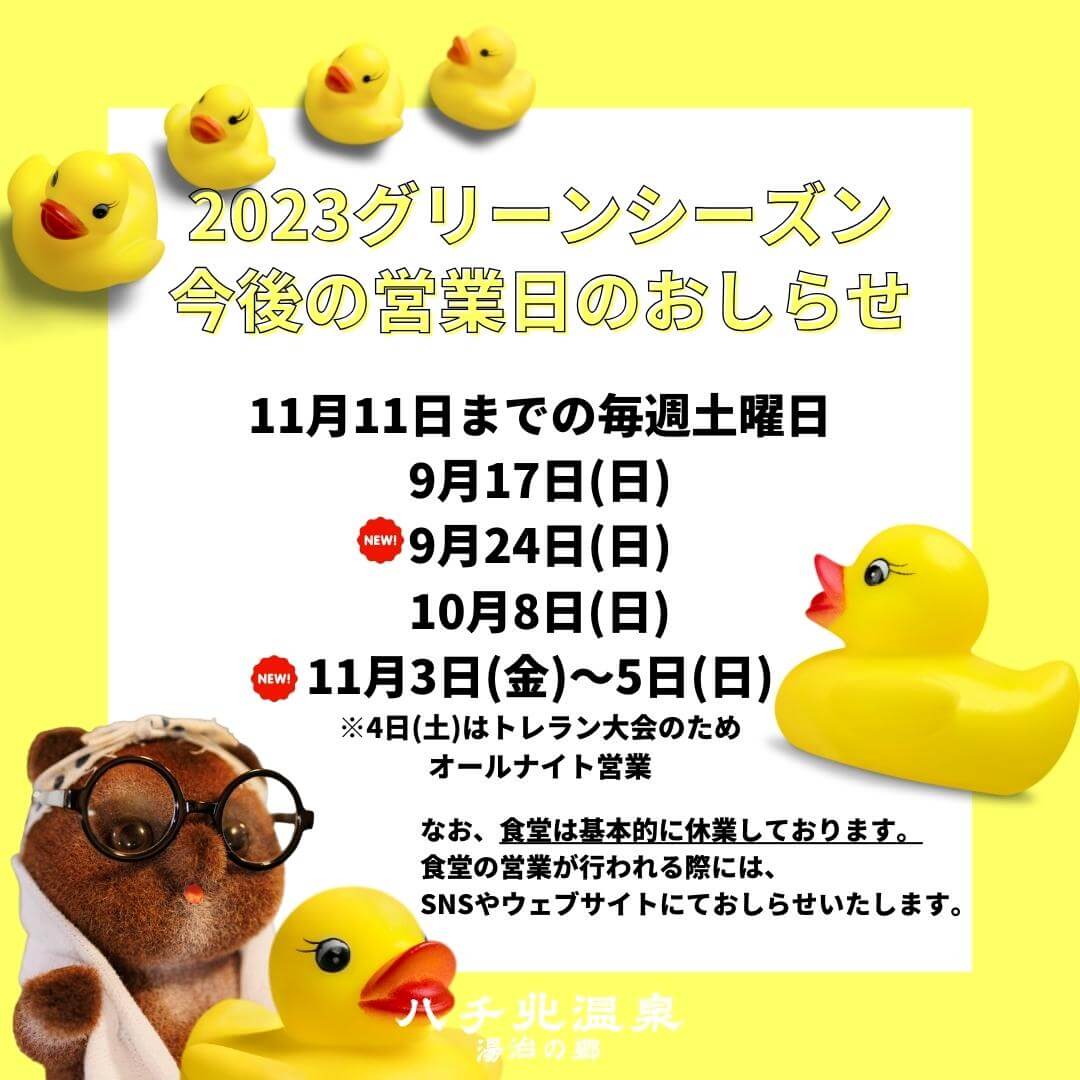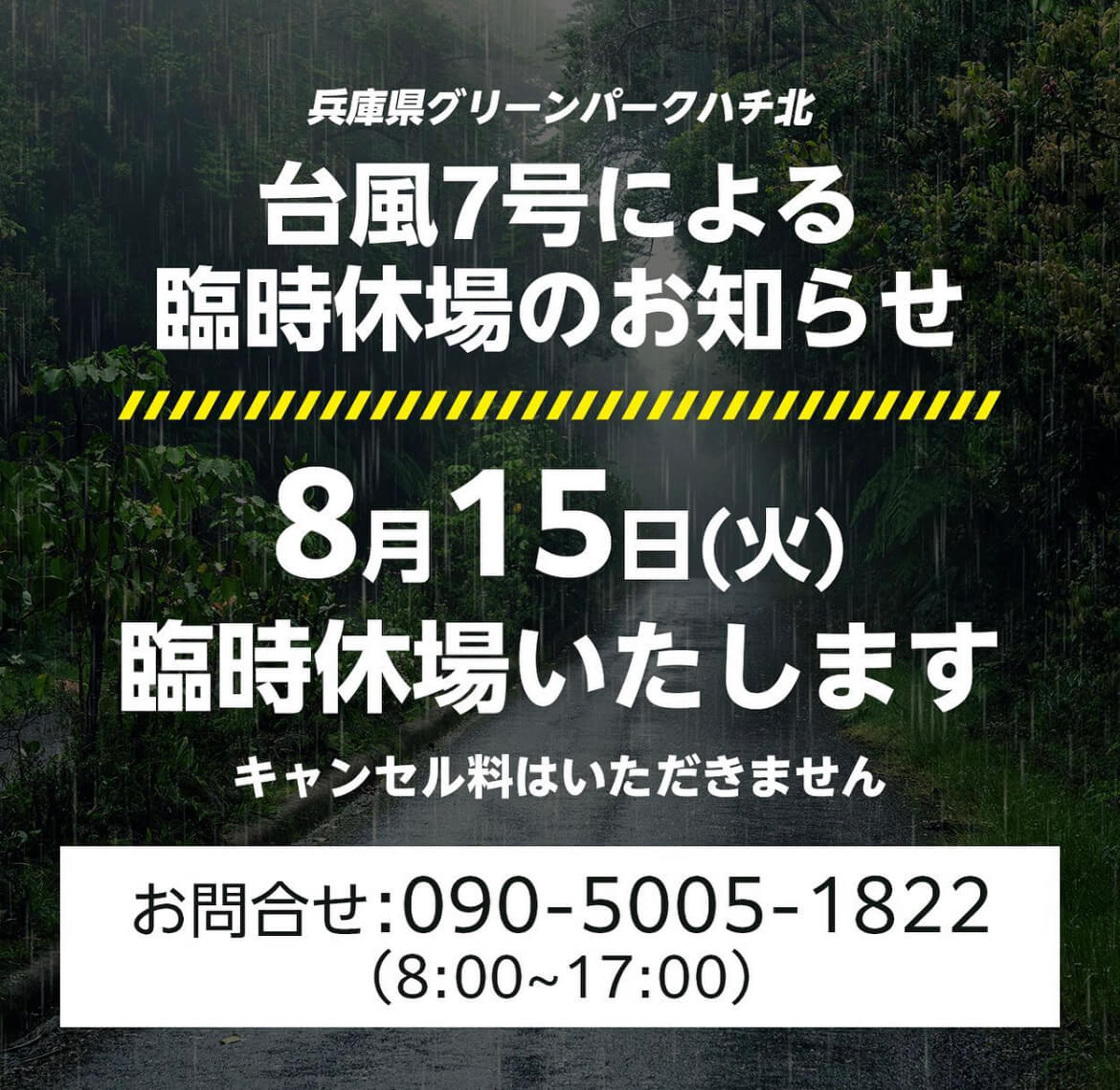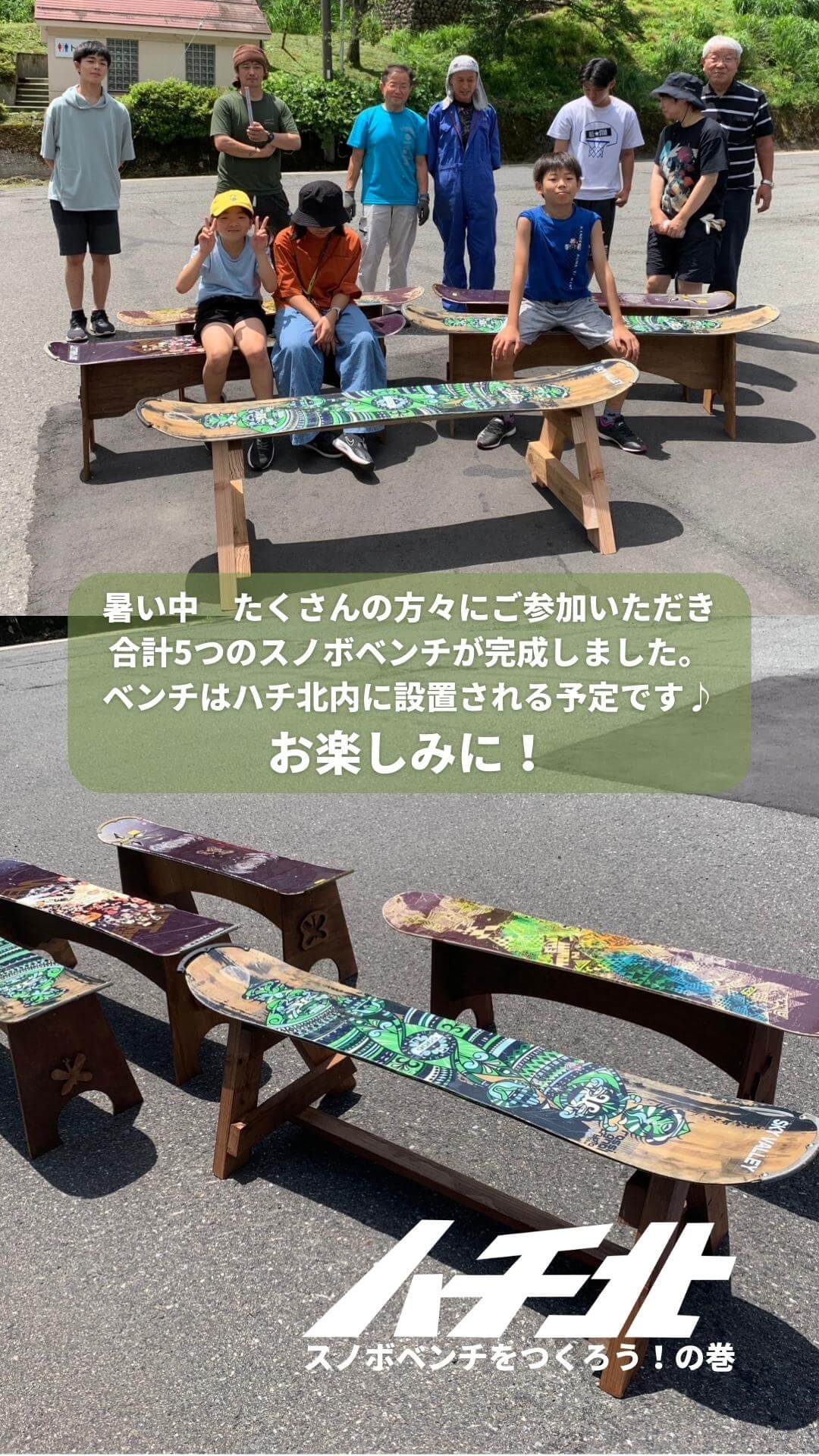全てのブログ
ハチ北旅館街 宿泊やレンタルショップのガイドマップ2024/12/13
2024-25年シーズンパンフレット 配布中です!
ハチ北スキー場旅館街の情報や、レンタルショップやレストランなども掲載しております。
ぜひご覧ください!(画像をクリックで拡大)
各旅館の詳細やご予約方法などは、香美町観光ナビをご覧ください!
お問い合わせ
ハチ北観光協会
TEL:090-5005-1822(8:00〜17:00)
e-mail:info@hachikita.green
連休の予定、決まりましたか?グリーンパークハチ北、今ならまだ空いてます!2024/06/26
連休の予定、決まりましたか?
いまならまだグリーンパークハチ北、空いてます🌳🌳🌳
熱くなることを予想して、下界から脱出🏃♀️
高標高の森の中で涼しくキャンプはいかがでしょうか🏕️
ホタルもちょうどいい時期かも…🤫💫
みなさんのご予約をお待ちしております🌿
ご予約はなっぷ [https://www.nap-camp.com/hyogo/13005]
からどうぞ👍
🌿〜🌼〜🏕〜🕊〜🍃〜✨〜🌳〜⛺️
キャンプサイトの空き状況など、
お気軽にDMやお電話でお問い合わせください🙋♀️
【ハチ北観光協会】
〒667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹15-1
0796-96-0732(8:00〜17:00)
ハチ北観光協会
🌿〜🌼〜🏕〜🕊〜🍃〜✨〜🌳〜⛺️
インスタフォローもお忘れなく💁♀️
@greenpark.hachikita
🌿~🌼~🏕~🕊~🍃~✨~🌳~⛺️
ハチ北温泉 湯治の郷 GW期間中の営業について2024/04/18

ゴールデンウィーク中のハチ北温泉・食堂の営業時間は、
🌟4月27日(日) 12:00~20:30
🌟4月28日(日)~5月5日(日) 11:00~20:30
🌟5月6日(月) 11:00~17:00
を予定しております。
また、その後のグリーンシーズンの営業につきましては、
基本的には下記の時間帯を予定しております。
♨️ 温泉 ♨️
土曜 12:00~20:30
日曜 11:00~17:00
🍴 食堂 🍴
日曜 12:00〜17:00
営業日時は変更になる可能性がございます。
必ず公式SNSや公式WEBサイトをご確認の上ご来館くださいませ。
グリーンシーズンのハチ北温泉 湯治の郷も、
いっそうのご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【結果発表】オガサカカップ第16回ハチ北ジュニア大会 2024年2月18日2024/02/18
2024年2月18日 ハチ北高原スキー場
オガサカカップ第16回ハチ北ジュニア大会
結果発表
【結果発表】第61回ハチ北アルペンスキー大会 2024年2月18日2024/02/18
【結果発表】第16回ハチ北スラローム大会 2024年2月17日2024/02/17
2024年2月17日 ハチ北高原スキー場
第16回ハチ北スラローム大会
結果発表
SAJ公認バッジテスト開催2024/02/08
2024年3月10日(日)9:00〜
ハチ北観光協会、村岡ハチ北スキークラブ共催のSAJ公認バッジテストを今年も開催します!ぜひご参加ください♪
日程
3月10日(日) ハチ北スキー場
受付
ハチ北スキー場 無料休憩所内 9:00~
講習・検定
- 講習 10:00〜 (2時間)
- 検定 13:00〜
種目
- 1級検定種目
- パラレルターン・大回り:ナチュラル・急斜面
- 基礎パラレルターン・小回り:ナチュラル・急斜面
- パラレルターン・小回り:不整地・中急斜面
- 総合滑降:ナチュラル・総合斜面
- 2級検定種目
- 基礎パラレルターン・大回り:ナチュラル・中急斜面
- シュテムターン・小回り:ナチュラル・中急斜面
- 基礎パラレルターン・小回り:ナチュラル・中急斜面
問い合わせ
090-1482-7109 (坂本)
1月4日(木)よりハチ北高原スキー場の営業を一時休止することになりました2024/01/04
平素より格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
積雪不足のため、本日2024年1月4日(木)よりハチ北高原スキー場の営業を一時休止させていただくこととなりました。
今後、ゲレンデの状況が回復次第再開予定とのことです。
お知らせは、
ハチ・ハチ北スキー場公式WEBサイト https://hachi-hachikita.co.jp
および公式Instagramアカウント @hachihachikita
また、当ハチ北観光協会アカウント @hachikita.view でも行って参りますので適宜ご確認いただけますと幸いです。
お問い合わせに関しましては、
■スキー場、リフトに関して
鉢伏開発観光株式会社(0796-96-0201)
■駐車場に関して
ハチ北観光協会(0796-96-0732)
までお寄せください。
お客様方にはたいへんご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、ハチ北高原スキー場、およびハチ北観光協会を何卒よろしくお願いいたします。